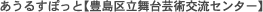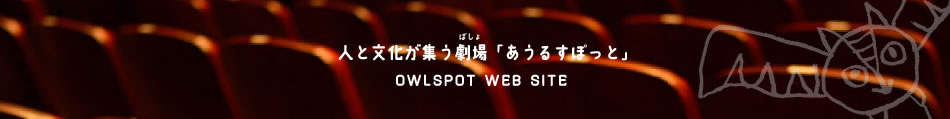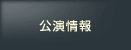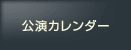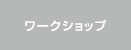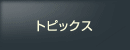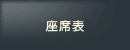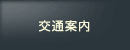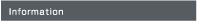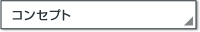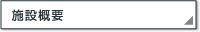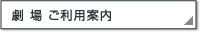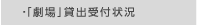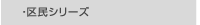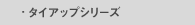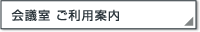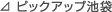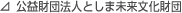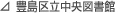ワークショップ・レクチャー
東京都立文京高校言語能力向上プログラム「コトバの教室」 開催レポート |
|---|
|
あうるすぽっとでは、教育プログラムを劇場の活動の柱と一つと位置づけ、その中で豊島区内の公立学校に出向き演劇やダンスのワークショップを行うアウトリーチ活動を行っています。 平成25年度は、豊島区内に所在する都立文京高校において「コトバの教室」と題し、1年生全員を対象としたワークショップを行いました。3回に渡り実施したワークショップの様子を、今回全面的に協力いただいた日本大学芸術学部の学生によるレポートでお届けします。
コーディネーター:熊谷保宏(日本大学芸術学部教授)
講師:絹川友梨、モーリー・ロバートソン、春原憲一郎 アシスタント:日本大学芸術学部の学生のみなさん、あうるすぽっとインターン 会場:都立文京高校視聴覚室 助成:平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業 |
| 第1回 2013年10月30日(水曜) 講師:絹川友梨 第2回 2013年11月6日(水曜) 講師:モーリー・ロバートソン 第3回 2013年11月13日(水曜) 講師:春原憲一郎 |
第3回 2013年11月13日(水) 講師:春原憲一郎 |
 3日目の講師は日本語教育の実践家であり研究者の春原憲一郎さん。テーマは「自分とは違う言葉や文化や考え方を持っている人とどうやって伝えあいをしてゆくか」とのことである。最初の自己紹介は「長年、日本語教師の仕事をやってきた」程度にとどめ、さっそく活動に入る。
3日目の講師は日本語教育の実践家であり研究者の春原憲一郎さん。テーマは「自分とは違う言葉や文化や考え方を持っている人とどうやって伝えあいをしてゆくか」とのことである。最初の自己紹介は「長年、日本語教師の仕事をやってきた」程度にとどめ、さっそく活動に入る。 生徒同士ペアとなり、二人の間に世界地図があるものと仮定し、春原さんが挙げてゆく国の位置を指差してゆくアクティビティー。まず、日本。どのペアも真ん中の少し上あたりを指さす。では、中国は? 日本の左を指す。といった具合に、どんどん挙げられてゆく国の位置を指さしてゆく。ブラジル、韓国、ペルー、台湾、ボリビア、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア、エジプト、オーストラリア、フランス、スリランカ、最後にケニア。ほとんどの生徒が指差しの見当すらつかない国を含むこれらの国々が、春原さんがこれまで日本語教育を実践してきた国であると聞くと、生徒たちからは驚嘆の声があがった。
生徒同士ペアとなり、二人の間に世界地図があるものと仮定し、春原さんが挙げてゆく国の位置を指差してゆくアクティビティー。まず、日本。どのペアも真ん中の少し上あたりを指さす。では、中国は? 日本の左を指す。といった具合に、どんどん挙げられてゆく国の位置を指さしてゆく。ブラジル、韓国、ペルー、台湾、ボリビア、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア、エジプト、オーストラリア、フランス、スリランカ、最後にケニア。ほとんどの生徒が指差しの見当すらつかない国を含むこれらの国々が、春原さんがこれまで日本語教育を実践してきた国であると聞くと、生徒たちからは驚嘆の声があがった。
 ケニアの公用語であるスワヒリ語において「こんにちは」にあたる言葉は何だろう?
ケニアの公用語であるスワヒリ語において「こんにちは」にあたる言葉は何だろう? と春原さんが生徒たちに問いかける。「ジャンボ」であることを確認したうえで、外国語によるコミュニケーションの体験へ。課題は、交換留学生としてケニアに行った日本人が、ケニア人の果物売り(おばさん)からフルーツを買う。ロールプレイングをおこなうわけだが、その際に使える言葉は「ジャンボ」のみ。挨拶のあとは、身振り手振りに頼るほかない。生徒たちは「外国人」として、コミュニケーションの苦労をしながらも、求める果物を食べる動作で表現してみるなどの工夫を楽しんでもいた。 買い物のために、もう一つ知っておきたい単語があるとしたら何だろうか? 要望が一番多かったのは「ありがとう」で、これは「アサンテ」。ついでに最上級「アサンテ・サーナ」も覚える。次に要望の多かったものが「いくらですか?」。ここで生徒たちはケニアでの通貨単位「シリンギ」を知る。せっかくなので、1から5までの数字もスワヒリ語で覚える……といった具合にボキャブラリーを増やすたびにロールプレイングを繰り返した。最後に「〜をください」というスワヒリ語「ニペ」を春原さんから教えてもらう頃には、文京高校生たちはもはや「スワヒリ語で買い物ができる」状態になっていたのである。 ここからは日本語に戻って、コミュニケーションにかかわる実験を試みた。たとえば、どれだけ長く相手の目を見たまま話を続けられるか。思うほど長くは続かない。あるいは、背中合わせに立った二人が相づちを打たずに会話ができるか。これは、まるで自分が無視されているような気持ちになる。目で、身体で人は会話をしているのだ。 つづいて、日常的な行為を細かく説明してゆくアクティビティー。「カップラーメンを食べる」という行為の過程を、十人ぐらいのグループのメンバーが順に説明してゆく。グループは、最後の生徒のところで食べる動作にたどり着くよう、細かな行為をうまく案配してゆかなければならない。たとえば、一人がカップラーメンの蓋を半分まで開け、次の人がヤカンに水を入れ、その次がコンロにかけ...といった具合である。なるべく細かく説明しようと思いながらも早々と「3分間待つ」状態に至ってしまったグループでは、おなかを空かせるため「運動をする」「踊る」といった案も出ていた。  最後に、日本人として外国人と関わるロールプレイングをおこなった。設定は、駅で切符の買い方の分からない(が、日本語が少しだけわかる)ベトナム人が日本人に声をかけてきた、というもの。切符が買えるように日本人役の生徒がサポートをおこなう。機械の使い方をジェスチャーで伝える生徒もいれば、相手の手をとり物理的に誘導する生徒もいる。これらも有効かもしれないが、ポイントは言葉だ。相手は「少しだけ」でも日本語がわかる人間なのであり、そもそも「話しかけて」きたのである。ベトナム人である彼(女)の話をどう聞くか、どう話すか。総じて生徒たちは「じっくり」聞き「ゆっくり」話し、仲良くなっていた。それでいいのだろう。「切符を買うのを手伝う」という行為が、単純に機能的なものではなく、コミュニケーションそのものだということを実感させられたアクティビティーであった。
最後に、日本人として外国人と関わるロールプレイングをおこなった。設定は、駅で切符の買い方の分からない(が、日本語が少しだけわかる)ベトナム人が日本人に声をかけてきた、というもの。切符が買えるように日本人役の生徒がサポートをおこなう。機械の使い方をジェスチャーで伝える生徒もいれば、相手の手をとり物理的に誘導する生徒もいる。これらも有効かもしれないが、ポイントは言葉だ。相手は「少しだけ」でも日本語がわかる人間なのであり、そもそも「話しかけて」きたのである。ベトナム人である彼(女)の話をどう聞くか、どう話すか。総じて生徒たちは「じっくり」聞き「ゆっくり」話し、仲良くなっていた。それでいいのだろう。「切符を買うのを手伝う」という行為が、単純に機能的なものではなく、コミュニケーションそのものだということを実感させられたアクティビティーであった。
まとめの話は、相手にとって「やさしい日本語」で話をすることの大切さについて。ていねいにゆっくりと、相手が理解していることを確認しながら言葉を選び、渡してゆくこと。外国人を相手にした場合のみならず、障害者や高齢者にも、その他さまざなま意味で「文化」の異なる人とのコミュニケーションにおいては「やさしい日本語」を心がけたい──と語られる春原さん。その授業プログラムは、バラエティーのあるものだったが、どの活動も(春原さんが使う意味での)「やさしい」コミュニケーションの大切さを確かめるものだったように思う。 文=伊藤景(日本大学芸術学部文芸学科) |