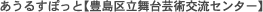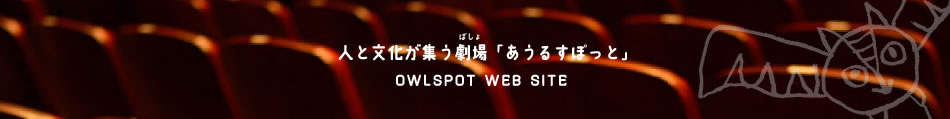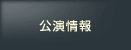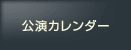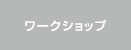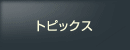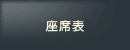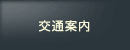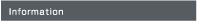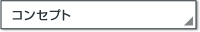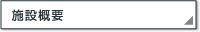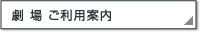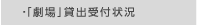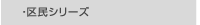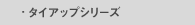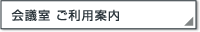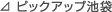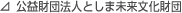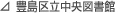ワークショップ・レクチャー
東京都立文京高校言語能力向上プログラム「コトバの教室」 開催レポート |
|---|
|
あうるすぽっとでは、教育プログラムを劇場の活動の柱と一つと位置づけ、その中で豊島区内の公立学校に出向き演劇やダンスのワークショップを行うアウトリーチ活動を行っています。 平成25年度は、豊島区内に所在する都立文京高校において「コトバの教室」と題し、1年生全員を対象としたワークショップを行いました。3回に渡り実施したワークショップの様子を、今回全面的に協力いただいた日本大学芸術学部の学生によるレポートでお届けします。
コーディネーター:熊谷保宏(日本大学芸術学部教授)
講師:絹川友梨、モーリー・ロバートソン、春原憲一郎 アシスタント:日本大学芸術学部の学生のみなさん、あうるすぽっとインターン 会場:都立文京高校視聴覚室 助成:平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業 |
| 第1回 2013年10月30日(水曜) 講師:絹川友梨 第2回 2013年11月6日(水曜) 講師:モーリー・ロバートソン 第3回 2013年11月13日(水曜) 講師:春原憲一郎 |
第2回 2013年11月6日(水) 講師:モーリー・ロバートソン |
 2日目の講師はモーリー・ロバートソンさん。初めに自己紹介として、ご自身の生い立ちを語られていったのだが、そのトークが凄い。この上なくスピーディーで、展開は自由かつ自在、そしてユーモア満載の、引き込まれる語りである。
2日目の講師はモーリー・ロバートソンさん。初めに自己紹介として、ご自身の生い立ちを語られていったのだが、そのトークが凄い。この上なくスピーディーで、展開は自由かつ自在、そしてユーモア満載の、引き込まれる語りである。アメリカで生まれ、5歳で日本へ移住。中学校の途中でアメリカへ戻り、高校の途中からは再び日本と、異なる文化を行き来しながら育つ。転校も多かった。移住や転校の度に経験した苦労や身に付けた知恵などが語られてゆくなかで、次第に授業のテーマに関わる「価値観の違い」という問題が浮かび上がってくる。その問題に大いに悩まされた日本での高校時代をくぐり抜け、東大、ハーバード大へ現役で同時に合格するに至ったストーリーに、生徒たちは拍手を送って盛り上がった。  自身のバックグラウンドを示し、テーマにも触れたところで、授業の説明へ。社会には、自分(たち)とは異なる価値観が存在する。相手の価値を否定することは簡単だが、対立する相手を説得する努力が必要な場合もある。本日おこなう「ディベート」も、相手を言い負かすことを目的とするものではない。まずは対立する意見にも耳を傾ける。そのうえで相手への説得を試みる。うまくすれば対立するものを味方につけることさえできる、そのような技術がディベートである、とのことであった。
自身のバックグラウンドを示し、テーマにも触れたところで、授業の説明へ。社会には、自分(たち)とは異なる価値観が存在する。相手の価値を否定することは簡単だが、対立する相手を説得する努力が必要な場合もある。本日おこなう「ディベート」も、相手を言い負かすことを目的とするものではない。まずは対立する意見にも耳を傾ける。そのうえで相手への説得を試みる。うまくすれば対立するものを味方につけることさえできる、そのような技術がディベートである、とのことであった。
ディベートのテーマは「男女平等」。予備知識として、モーリーさんが、男女比に関する国際的な統計データを紹介していった。国会議員数、会社における役員の数、そして大学の教員数など、社会的な地位が高いとされる職業に占める女性の比率が日本では少ないことを確認したうえで、モーリーさんが問いかける。国立大学の学生の男女比を(アメリカのハーバードやイェール大学のように)51:49 にしたらどうか? ちなみに東大生の男女比は8:2である。  生徒たちは5人ずつ(男女混合)のグループをつくりディスカッションをおこなうことになった。実際の議題は「来年から国立大学の学生数や教授数を 51:49 の男女比率にする」と、より具体的なものとなる。まずはグループ内で、それぞれの主張や見解を交換しあってみる。そのうえでグループごとに発言者を決め、どのような意見があったのか発表していった。ほとんどのグループがデメリットが多いとし、男女の比率を平等にすることに反対していた。入学してくる人数を制限することは可能だが、元からいる男性教師を解雇することになるのだから失業者が増えるのではないだろうか。未経験者が増え、授業のレベルが下がるのでは、など。なかなか現実的だ。
生徒たちは5人ずつ(男女混合)のグループをつくりディスカッションをおこなうことになった。実際の議題は「来年から国立大学の学生数や教授数を 51:49 の男女比率にする」と、より具体的なものとなる。まずはグループ内で、それぞれの主張や見解を交換しあってみる。そのうえでグループごとに発言者を決め、どのような意見があったのか発表していった。ほとんどのグループがデメリットが多いとし、男女の比率を平等にすることに反対していた。入学してくる人数を制限することは可能だが、元からいる男性教師を解雇することになるのだから失業者が増えるのではないだろうか。未経験者が増え、授業のレベルが下がるのでは、など。なかなか現実的だ。
モーリーさんが生徒の意見をジャッジすることはない。ひとつひとつの意見を咀嚼し、また論点を整理しつつ、議論を前に進めてゆくファシリテーターの役割に徹している。一方しかるべきタイミングで、新たな問いを生徒たちに投げかけもする──そもそも男女は平等であるべきなのか? 平等であるメリットとデメリットは? 先ほどの、大学の場合とは反対に、メリットの意見が多く出る。では、と、モーリーさんが問いかける──妥協案として、少しずつでも男女の比率を平等に近づけてゆくにはどうしたらよいか...といった具合に、新たなトピックも加えつつ、問題を多面的に検討していった。  ディベートの区切りごとに、テーマである「男女平等」をめぐって、モーリーさんから新たな視点の提示がある。たとえばイスラム社会における男女の分離について。その宗教的背景や女子教育の現状、それに対抗する個人やメディアの活動...等々が紹介された。情報量は(高校の授業ではあまり扱われない類の事実や事例も含め、かなり)多めであったものの、生徒たちが集中し続けられたのは、今回のテーマをめぐるディベートにはグローバルな知識や認識が必要であるとの自覚が、すでにできていたからだと思う。
ディベートの区切りごとに、テーマである「男女平等」をめぐって、モーリーさんから新たな視点の提示がある。たとえばイスラム社会における男女の分離について。その宗教的背景や女子教育の現状、それに対抗する個人やメディアの活動...等々が紹介された。情報量は(高校の授業ではあまり扱われない類の事実や事例も含め、かなり)多めであったものの、生徒たちが集中し続けられたのは、今回のテーマをめぐるディベートにはグローバルな知識や認識が必要であるとの自覚が、すでにできていたからだと思う。
終盤におこなったのは「男女平等を強制的におこなうことに対して賛成か反対か」のチームディベート。賛成派と反対派のチームに分かれ、まずはチーム内で論点を整理し、のち代表者が発表する。 反対派「選抜は、学力でおこなうべきだ。男子の方が能力的に優位であるから、男女平等を強制することは難しいのではないだろうか」 賛成派「それは偏見である。女性の活躍できる場を強制的に増やせば、その能力も認められてゆくはずだ」 反対派「女性は産休の際に一度職場を離脱しなければならない。そこで新しく入ってくる女性社員に一から仕事を教えなければいけないから、会社の負担が大きい」……  議論は続く。もっと続けたいところだが、ディベートなので規定の時間で打ち切る。どちらを支持するかクラスのみんなに問う。もらった拍手の量は、どちらも多く、甲乙つけがたい。ということは、良いディベートだったと考えるべきであろう。
議論は続く。もっと続けたいところだが、ディベートなので規定の時間で打ち切る。どちらを支持するかクラスのみんなに問う。もらった拍手の量は、どちらも多く、甲乙つけがたい。ということは、良いディベートだったと考えるべきであろう。
ディベートのよいところは、普段は考えない、あるいは考えないようにしている事柄について考えることができる点だとモーリーさんは語る。その際に、自分の考えとは異なる意見にも出会う。そもそも、対立する立場を設定して討論をおこなうのがディベートであるから、意見はぶつかり合う。ぶつかり合う意見、自分とは異なる意見に耳を傾けることの大切さを、モーリーさんは繰り返し強調する。異なる意見を聞き入れる耳をもった世代が育つと、日本は良くなる──このモーリーさんの言葉を、生徒の誰もが自分たちに向けられたメッセージとして受け止めていた様子が見て取れ、心強かった。 文=伊藤景(日本大学芸術学部文芸学科) |