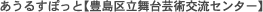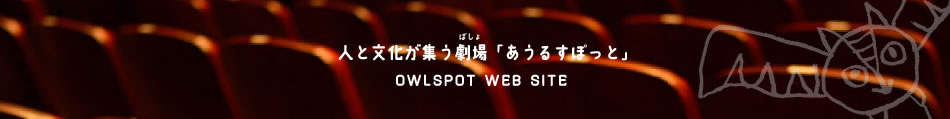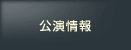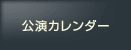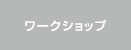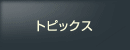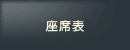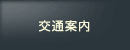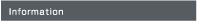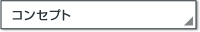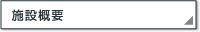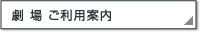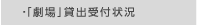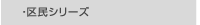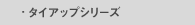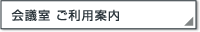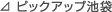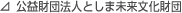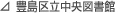ワークショップ・レクチャー
東京都立文京高校言語能力向上プログラム「コトバの教室」 開催レポート |
|---|
|
あうるすぽっとでは、教育プログラムを劇場の活動の柱と一つと位置づけ、その中で豊島区内の公立学校に出向き演劇やダンスのワークショップを行うアウトリーチ活動を行っています。 平成25年度は、豊島区内に所在する都立文京高校において「コトバの教室」と題し、1年生全員を対象としたワークショップを行いました。3回に渡り実施したワークショップの様子を、今回全面的に協力いただいた日本大学芸術学部の学生によるレポートでお届けします。
コーディネーター:熊谷保宏(日本大学芸術学部教授)
講師:絹川友梨、モーリー・ロバートソン、春原憲一郎 アシスタント:日本大学芸術学部の学生のみなさん、あうるすぽっとインターン 会場:都立文京高校視聴覚室 助成:平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業 |
| 第1回 2013年10月30日(水曜) 講師:絹川友梨 第2回 2013年11月6日(水曜) 講師:モーリー・ロバートソン 第3回 2013年11月13日(水曜) 講師:春原憲一郎 |
第1回 2013年10月30日(水曜) 講師:絹川友梨 |
 午後1時。教室に、昼休みを終えた生徒たちが続々と集まってくる。40 人のクラス1つなら十分に体育館としても使えるサイズの視聴覚教室も、3クラスが集まると窮屈そうだ。教室前方のスクリーンには「コミュニケーションってなんだろう?」...さて、なんだろう?
午後1時。教室に、昼休みを終えた生徒たちが続々と集まってくる。40 人のクラス1つなら十分に体育館としても使えるサイズの視聴覚教室も、3クラスが集まると窮屈そうだ。教室前方のスクリーンには「コミュニケーションってなんだろう?」...さて、なんだろう? 本日の講師である絹川友梨さんによれば、重要なことは3点。まずは自分から「伝える」こと。2つ目は相手から「受け取る」こと。最後が「続ける」こと。そのためのエクササイズは何より「楽しんで」とのメッセージが伝えられ授業スタートである。
まずはウォーミングアップのゲーム「拍手まわし」。教室の縦方向1列(十数人)が1グループとなり、前の人から後ろの人へと拍手を送ってゆく。グループ間でその速度を競うわけだが、何より拍手を「確実に」送り、受け取ることが必要だ。
本日の講師である絹川友梨さんによれば、重要なことは3点。まずは自分から「伝える」こと。2つ目は相手から「受け取る」こと。最後が「続ける」こと。そのためのエクササイズは何より「楽しんで」とのメッセージが伝えられ授業スタートである。
まずはウォーミングアップのゲーム「拍手まわし」。教室の縦方向1列(十数人)が1グループとなり、前の人から後ろの人へと拍手を送ってゆく。グループ間でその速度を競うわけだが、何より拍手を「確実に」送り、受け取ることが必要だ。
 拍手を「確実に」送り、また受けるために、相手に対し身体ごと向き合い、アイコンタクトも合わせるなどの工夫を加えてゆく生徒たち。一方で、競争心から「早く早く!」などの声援もさかんに飛び交い、教室は早くも熱気を帯びた。
拍手を「確実に」送り、また受けるために、相手に対し身体ごと向き合い、アイコンタクトも合わせるなどの工夫を加えてゆく生徒たち。一方で、競争心から「早く早く!」などの声援もさかんに飛び交い、教室は早くも熱気を帯びた。
からだも温まったところで、第一の要点「伝える」ことにフォーカスしたエクササイズへ。与えられたテーマを、ことばを用いず、身体的な表現だけで相手に伝える、というものである。まずはペアで「好きなスポーツ」などのお題を練習。 その後グループになり、より複雑な、物語性のある内容へと入っていった。絹川さんからの例題は...「お腹が空いたので、コンビニに行って、シャケのおにぎりを買いました。レジでお金を払おうとしたら、なんとお財布を忘れてきたことに気がつきました」。 さて「コンビニ」をどう表現するか? 「シャケ」は? また全体をひとつの物語として表すには? 苦労しながらも工夫して、身振り手振り、また表情も活用しつつジェスチャーによる表現を探ってゆく。正確に伝わり、手を取りあって喜ぶチーム。うまく伝わらず、しかしメゲず、再挑戦を繰り返すチームも見られた。 中盤は、第二の要点「受け取る」ことに焦点を置く流れとなった。中心となったエクササイズは「リーダー&フォロワー」である。2人組のペアを作り、導き手の「リーダー」が導かれる「フォロワー」の手を取り、誘導しながら教室を歩き始める。フォロワーはリーダーを信じ、身を任せる。リーダーはフォロワーを受け止め、フォロワーの発するメッセージを受け取りつつ、導いてゆかねばならない。周囲にも気を配らないと衝突する危険性もある。  ペアの歩みは、初めは総じて恐る恐るであったが、徐々に滑らかに、あるいは力強くなってゆくなど、変化してゆくのがわかる。途中でリーダーとフォロワーの交代。フォロワーが目を瞑る、リーダー同士が途中で交代する、などのバリエーションも試みられた。
ペアの歩みは、初めは総じて恐る恐るであったが、徐々に滑らかに、あるいは力強くなってゆくなど、変化してゆくのがわかる。途中でリーダーとフォロワーの交代。フォロワーが目を瞑る、リーダー同士が途中で交代する、などのバリエーションも試みられた。
この「リーダー&フォロワー」のあいだ、また振り返りにおいて絹川さんが強調されていたのは、相手の立場に立ち、共感することの大切さである。その考えが自分とは違うものであっても、相手を尊重すること。その立場を想像し、共感すること。コミュニケーションにおいては、そのような尊重や共感が重要であるとのメッセージが込められたエクササイズだったのである。  終盤のフォーカスは第三の要点であるコミュニケーションを「続ける」こと。「シェアードストーリー」という、グループで物語を紡いでゆくエクササイズをおこなった。
終盤のフォーカスは第三の要点であるコミュニケーションを「続ける」こと。「シェアードストーリー」という、グループで物語を紡いでゆくエクササイズをおこなった。
4〜5人のグループを作り「指揮者」を1人決める。指揮者は、まず「昔々あるところに〇〇な〜〜がおりました」と、物語のオープニングを語る。そこから先の話は、指揮者に指さされたメンバーが即興で作り、語ってゆくことになる。その語りは、指揮者が他の誰かを新たに指さすまで止めることはできない。一方で新たに指さされた人は、そこまで語られた話をすかさず引き受け(それがセンテンスの途中であろうとも)文を完結させ、またその先を語り続けなければならない。その語りの途中で指揮者はまた別の誰かを指名し....と、ひとつの物語を集団で、しかも即興で作ってゆく、というものだ。その即興性の流れ、成り行きを握るのは指揮者で、その指さしのタイミングと相手によって、話の運びは思いもよらぬものとなる。実にスリリングだ。  ひとつの話ごとに指揮者が代わり、テーマも変わる。絹川さんが示すお題のパターン、たとえば「不思議な◯◯」や「◯◯の初恋」を受け、グループが◯◯を決める。そこから先は自在な指揮と自由な即興となる。空を旅する「不思議なスリッパ」や、席替えをキッカケとした「机の初恋」といった、オリジナルな物語が次々と生まれていった。
ひとつの話ごとに指揮者が代わり、テーマも変わる。絹川さんが示すお題のパターン、たとえば「不思議な◯◯」や「◯◯の初恋」を受け、グループが◯◯を決める。そこから先は自在な指揮と自由な即興となる。空を旅する「不思議なスリッパ」や、席替えをキッカケとした「机の初恋」といった、オリジナルな物語が次々と生まれていった。
人の話を聞き、引き受け、さらに発展させてゆく。この方法・思想のことを、絹川さんが専門とするインプロ(即興演劇)の世界では「イエス・アンド!」という。「イエス」とは、相手の話を否定せず、肯定的に受け入れること。「アンド」は相手の意見に自分のアイデアを足していくことである。これは日々のコミュニケーションにおいても有効な考えであろう。つねに心がけておきたいものと思った次第である。 すべてのエクササイズを終えた生徒たちのテンションは、授業が始まった時より高い。身体を活発に動かしたことだけが理由ではないだろう。より内面的な高揚があったのではないか。それこそ、ほかならぬ「コミュニケーション」についての新たな学びがもたらしたものであり、この時間に絹川さんが伝えたかったもののように思われた。生徒たちはそれを確実に受け取ったのではないか。 文=伊藤景(日本大学芸術学部文芸学科) |