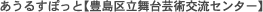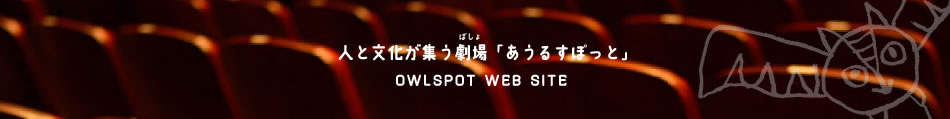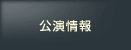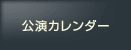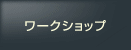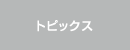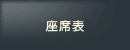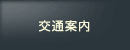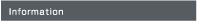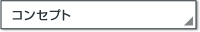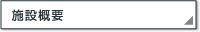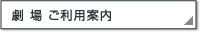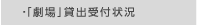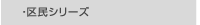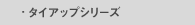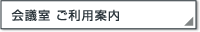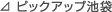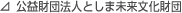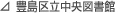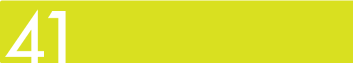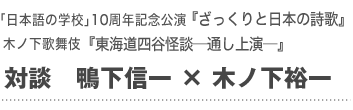トピックス・インタビュー41
|
年の差50歳の対談が実現!
テレビドラマのディレクターを出発点に、独自の朗読舞台の演出などで活躍する鴨下信一さんと、豊富な知識を活かし、歌舞伎を多彩な手法で現代化して高く評価される木ノ下歌舞伎主宰・木ノ下裕一さん。お二人は以前から、あうるすぽっとを創作や公演の場に活用して下さり、今年5、6月は木ノ下歌舞伎『東海道四谷怪談―通し上演―』と、鴨下さんが長年続けて来られたワークショップ「日本語の学校」10周年記念朗読公演で続けて登場します。「日本語」と向き合い、その魅力と変化を核として創作を行うお二人の、今の想いをうかがいました。
 |
――お二人で話されるのは今日が初めてですね。 鴨下:ええ。でも歌舞伎をやってらっしゃるだけで安心できたし、良い人に違いないと思って今日は来ました(笑)。僕、大学の卒業論文が歌舞伎でね。 木ノ下:どんな研究をされたんですか? 鴨下:特定の作家・作品ではなく「一人二役の研究」というもの。ただ、指導教官がヘーゲリアン(18世紀ドイツの哲学者ヘーゲルの研究者)で、海外の文献や事例に当たるところが少ない、専門外の僕の論文は厄介もの扱いでした。 木ノ下:実は僕、以前から鴨下さんを大尊敬していまして、今日は神様に会うような気持ちで参りました! 鴨下:そんなことを言われると、先が長くないみたいだな(笑)。 木ノ下:いえいえ、まだまだ活躍していただきたいんですが(笑)、とにかく鴨下さんのテレビドラマが大好きで。昭和60年(1985年)生まれなので、リアルタイムではない作品も多いのですが、DVDで繰り返し見るほどハマりまして。 鴨下:……マイったね、50歳違いですよ。 木ノ下:特に『岸辺のアルバム』(77年)は、どうしたら、あれほどの作品がつくれるのかと感動しました。 鴨下:あれは山田太一さんの脚本がとにかく良かった。演出家は何もしなくてもいいと思うほどで、撮影も楽だった記憶があります。しかし『東海道四谷怪談』は難しい題材でしょう。 木ノ下:はい、情報量が膨大な作品ですから。 鴨下:僕、テレビドラマにしたことがあるんです、『新・四谷怪談』というタイトルで。 87年の「東芝日曜劇場」でした。 木ノ下:惜しい! 僕は2歳です(笑)。 鴨下:調べるなかで、作者の鶴屋南北が作品の宣伝に「生首をくわえた女の絵を描いた大凧を作り、揚げさせた」という記述をみつけて、その画を撮りたくてね。ドラマの冒頭に入れましたけれど。 木ノ下:南北はプロデューサー気質というか、宣伝が上手い。劇中に早替わりがあると「キリシタンの妖術を使った咎(とが) でお上の取り調べが入った」という噂を流し、前評判を取るなんてこともしたとか。 鴨下:端々まで役者を上手く使っているしね。 木ノ下:当時座付作家をしていた中村座には、主役級ではないけれど、魅力的な役者が多かったそうで、だから主筋に関係ない場面も多かったのでしょう。 |
 |
――木ノ下歌舞伎では旗揚げ作品が『〜四谷怪談』ですね。 木ノ下:ええ、旗揚げは二幕目の抜粋上演でしたけれど、僕と杉原邦生さんがそれぞれに演出して。鴨下先生のお考えはわかりませんが、『〜四谷怪談』は僕には“歌舞伎っぽくない”感じがするんです、読んでいて。キャラクターの内面が複雑なうえ、非常にしっかり立っていて、手順や様式で見せなくても成立する。むしろ現代の俳優が演じたほうが、観客にリアルに伝わる面もあると思うんです。そこに突破口があると考え、旗揚げ作品に選びました。もちろん、そんなに簡単にはいきませんでしたけれど(笑)。 鴨下:僕は白石加代子さんと『百物語』など、長く一緒に朗読の舞台をつくっていて、それが高じてここ、あうるすぽっとで続けている「日本語の学校」というワークショップまでやっているんです。加代子さんとの仕事では、『〜四谷怪談』も当然候補にはなった。でも、周囲が「(加代子さんが演じたら)リアルで怖すぎるだろう」と言い実現しなくて(笑)。ただ、寄席などでやる講釈種のお岩さんの話は今でもやりたい、あれは歌舞伎の比ではないほど怖いでしょ? 木ノ下:確かに。あちらのほうが南北より古いという説もあるし、 元になった「四谷雑談集」に内容も近くて。 鴨下:お岩さんの母親の話から始まるのだけれど、それがまた怖い。「お岩誕生」というね。 木ノ下:あの因縁話はまるで『リング』(鈴木光司のホラー小説)に出てくる貞子ですよ。 ――南北の言葉を鴨下さんはドラマの脚本に、木ノ下さんは部分的にまったくの現代語に移す作業をしてらっしゃいますが、その際に感じたハードルはありましたか? 鴨下:ハードルはないんですよ、本が非常によく書けているから。ただせりふのテンポが、当時どうだったのかは知りようがない。そこは気にしながらやりましたね。かなりの速度だと思うのだけれど。 木ノ下:そうですね、今の歌舞伎のスピードで『〜四谷怪談』全幕原作通りでやると10時間はかかる。しかも、初演当時は『仮名手本忠臣蔵』と、その裏話としての『〜四谷怪談』を入れ子で半分くらいずつ、二日かけて上演したわけで、現在の歌舞伎のせりふ回しではとても上演し切れなかったと思います。時代物は速く、世話物はゆっくりと、演目によって速度を変えていたんでしょう。また、「歌舞伎俳優が一番言いにくいのは南北のせりふ」という説がありますよね? 鴨下:ありますね。 木ノ下:それで、「コレは僕らにも勝ち目がある」と思ったんです。南北のテキストを見ていくと、生世話物ですから、せりふ全体は当時の現代口語に近いし速い。でも核となる民谷伊右衛門、お岩夫妻にちょっかいを出す伊藤家の人々は、非常に侍ばった喋り方をするなど、一作の中にいろいろな言語体が入っているんです。2013年の通し上演では、それを色分けし、当時の現代口語を現代語に書き換えるなど、南北がもともと書き分けていた三層くらいの言語構造を、現代にずらした台本を作りました。歌舞伎原文のせりふ、歌舞伎と現代口語がちゃんぽんの部分、完全に我々の日常口語の部分、と。 鴨下:モザイク効果だ。なるほど面白い! 次回、是非拝見したいと思います。 木ノ下:光栄です!! |
 鴨下:上演するとき、ちゃんとお参りには行った? 木ノ下:もちろんです。2006年の旗揚げも、初めて通し上演をした13年も、新宿区四谷左門町にある於岩稲荷田宮神社と於岩稲荷陽運寺へ。でも二人だけ行けないスタッフさんがいて。そうしたら、公演中に原因不明の機材トラブルに見舞われたり……いろいろありました。 鴨下:怖いねぇ。でもあるんだよ。僕のドラマも皆でお祓いにと時間を作ったのに、スタッフの若い子が一人、車の整理をしていてお参りできなかった。そうしたら撮影中、カメラのレール設置作業でその彼が膝をバックリ切る怪我をしてね。あるんですよ、わかりやすく、そういうことが。日本には「たたり神」がたくさんいて、無関係な人まで被害を被る。不条理な出来事を社会的に処理するための、ある種の発明ですね。 木ノ下:はい、日本の社会や文化では基本ですね、「たたり」は。 鴨下:こういう、木ノ下さんの歌舞伎作品や言葉への細やかなこだわりを聞いていると、嬉しくなりますね。僕はテレビ局での仕事のあと、朗読作品をつくることにハマり、さっきもお話しした「日本語の学校」というワークショップまで始めてしまったのだけれど、ドラマや演劇の現場で、物事がわからなくなったときは、朗読をさせるのが一番効果的な対処法だと思っているんです。演技云々より、音声芸術に戻すこと、と言えばいいかな。 木ノ下:なるほど。 |
|
鴨下:それは、日本語の現状は非常に危ういと思ったから。もちろん言葉は年月とともに変わるものですが、最近は教師やアナウンサーなど、言葉のプロというべき人たちの日本語も無惨なもの。オノマトペ(擬音語、擬態語)がほぼ全滅しているでしょう? 誰も「雨がシトシト降る」なんて言わなくなった。 木ノ下:確かに。なんでも「バーッ、ガーッ」というような、勢いだけの雑な表現が増えましたね。 鴨下:この前サッカー中継を聞いていたら、ゴールが決まるたびにアナウンサーと解説者が一緒になって、ただ「ワーッ!」と叫ぶんです。蹴った角度やボールの方向、ゴールが決まった情景を言葉にしてくれないと、絵が見えなければ何も伝わらないのに。 木ノ下:僕もリオ五輪をラジオでずっと聞いていましたが、実況はヒドいものでした。アスリートの皆さんは尊敬しますし、スポーツの意義もわかるのですが、自国の活躍ばかりを強調する実況を聞いていると、国と国との争い、戦争の代替行為のように思えてきて。昔からこういうものだったのかと、思い立って前回の、64年の東京五輪の実況記録を聞いてみたら全く違いました。実に平等で格調高く、絵が浮かぶように喋っていました。 鴨下:そうそう、立派なものですよ。「ワーッ」なんて適当なことは言わない(笑)。
平成に入って、日本語は本当に大きく、悪いほうへ変わっていると思います。それ以前に日本語が大きく変わったのは明治の、夏目漱石が執筆活動を始めたころかと思いますが、漱石も盛んに朗読を推奨していたそうですよ。
木ノ下:近代以降、一番衰えた人間の身体的機能は「耳」、聴く力だと思うんです。ビジュアルは映像の分野などで見せる側も色々進化していますが、こと聴くことにかけては弱る一方かと。 鴨下:確かに「聴く力」は衰えてますね。結果、俳優のせりふを言う力も衰えている。抑揚がないうえに、ボソボソボソボソ言うばかりで、恐るべき時代ですよ。発語スピードが速すぎて全体に子音が弱くなって、言葉を互いに聴き取りにくくなっているし、圧倒的にボキャブラリー(語彙)が少ない。だから演劇に、身体性が求められる傾向が強まっているんじゃないでしょうか。ただ座ったまま喋っても伝えられないし、芝居が成立しないから。 木ノ下:恐ろしいことですね。 |
 |
|
鴨下:恐ろしい、演劇はそのうち滅びるかも知れない。とはいえ、僕も偉そうなことを言えた義理ではないんです。東京生まれの東京育ちで、地域の言葉、方言はとんと喋れないし詳しくもない。以前ね、自然薯のとろろが名物の静岡の丸子(まりこ)という場所を紹介しているテレビを見ていると、アナウンサーが頭の「ま」にイントネーションを置く、人名の「真理子」などと同じように発語したんです。「間違ってらぁ」と思って聴いていたら、地元の方が出ていらして同じイントネーションで地名を発語した。間違っていたのは僕のほうだったんです。 木ノ下:面白いですねぇ。 鴨下:そんなことを考え出したら、にわかに教えることに自信が持てなくなった。演劇は難しい。紙に書いてあることを、無理やり音にする商売だから。これが、僕が身を入れて朗読をやるようになったきっかけの出来事なんです。 木ノ下:江戸の半ばまでは関西の言葉が標準語でしたから、ありえることですよね。義太夫の太夫さんなんか、標準語に引っ張られた箇所を「訛った」と今も仰います。義太夫のイントネーションは関西が基本ですから。 鴨下:今度の朗読公演のテーマが「日本の詩歌」なので、万葉から近現代まで様々な詩歌を選んでいるけれど、まぁ大変です。折角ならと「万葉からは春夏秋冬、季節ごとに選ぼう」などと自分でくくりを設けたら、すっかりはまり込んでしまって。 木ノ下:僕が鴨下先生の作品に強く魅かれるのは、ドラマという「画」のある表現なのに、優れて「音」に敏感でいらっしゃる、そのことが大きいということに、お話を伺いながら改めて気づきました。『岸辺のアルバム』でもありましたよね。竹脇無我さんと八千草薫さんが電話で話すシーン。その会話を、スーパーで買い物する八千草さんの姿に重ねていらっしゃいましたよね? それが電話の前の回想か、電話のあとの光景か微妙にわからない不思議なシーンで。あの演出はスゴイです、舞台では絶対できない、見るたび悔しくなります。耳で聴かないとシーンやあの画の意図はわからない、音と画が切り離せないようにできている。 鴨下:心象風景か現実かわからない。太一さんのホンが上手いから、演出家としてはああいうふうにしか撮れないんですよ。なんというか……あの作品は、最も上質なドキュメンタリーなんです。 木ノ下:確かに! 特に前半はドキュメンタリー的ですね。 鴨下:そう、あと最終回。僕はドラマよりドキュメンタリーが好きな人間ですから、演劇は好きですけれどね。 木ノ下:複眼レンズを持った作家ですよね。お岩さんと伊右衛門はどちらかというとサブストーリーで、妹のお袖と直助のほうが本来は物語の主軸じゃないですか。 鴨下:そうそう。あとは伊右衛門に横恋慕する、伊藤家の孫娘・お梅ね。伊藤家の人々のシーン、あそこは面白いよね。 木ノ下:はい、普通の人の狂気が一番怖いというのがリアルに伝わって来ます。伊右衛門は悪事に多少なり罪悪感がありますが、伊藤家の人々にはありませんから。 鴨下:確かに。加えて、最初に話したプロデューサーとしてのセンスが南北にはあるからね。 ――お二人の基盤にあるもの、舞台に乗らない作品の背景にあたるところに、いかに豊かな知識や学識、経験の蓄積があるかが、限られた時間の中でも伝わって来ました。上演作品に関わらず、お二人のトークそのものが知的エンタテインメントになると思うのですが。 鴨下:面白いね! やりましょうよ。 木ノ下:嬉しいです!! コンビ名は「日本語を憂う世直しの会」でいかがでしょうか(笑)。 取材・文:尾上そら 写真:大橋 愛 |
| INFORMATION |
|---|
鴨下信一「日本語の学校」10周年記念公演
|