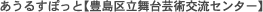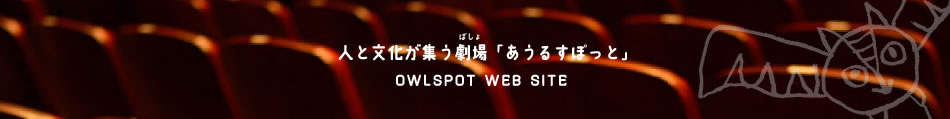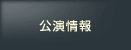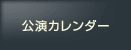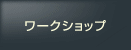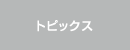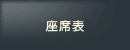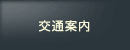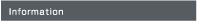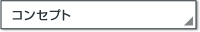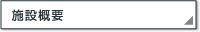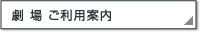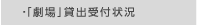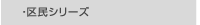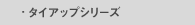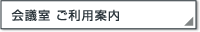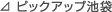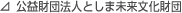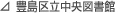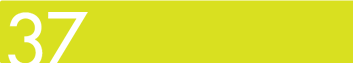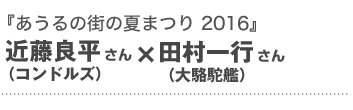トピックス・インタビュー37
|
これまでも幅広いお客様に向け、多彩な作品を発信してきたあうるすぽっとですが、今年の夏は、さらにラインナップを充実させた、おとなとこどもが一緒に楽しめる夏まつりを計画しています。「あうるの街の夏まつり 2016」と題し、7〜8月末までの1ヶ月半に、7作品がエントリー。その中で、劇場を飛び出し、夏の行事として広く人気を集める『にゅ〜盆踊り』の生みの親、コンドルズの近藤良平さんと、新作『はだかの王様』を振付・演出する舞踏集団・大駱駝艦の田村一行さんの対談が実現しました。「踊り」をめぐる二人の会話は、作品同様楽しく自在に広がっていきます。
 |
――近藤さんは最近、田村さんもご出演だった大駱駝艦の公演『クレイジーキャメル』をご覧になったそうですね。 近藤:そう、すっごい面白かったんですよ。あれは金粉を全身に塗っているダンサーさんが多い構成だったけれど、普段の、白塗りだけの作品と定義が違ったりするのかな? 田村:普段の作品では、内に向かって行くような要素も多いですが、金粉の時は発散していく感じが強いですね。僕が振付する場合でも、意味などを重視して動きをつくるというより「金色の身体がこう動いたらきれいだな」とか、どうやったら見てる人が飽きないかとか、そういうことを気にしてつくる感じで、根本の発想からして違います。 近藤:わかる、すごくショウとして「魅せる」印象があったもの。麿さん(麿赤兒・大駱駝艦主宰)や田村君とか白塗りの人も少しいて、いつもはインパクト絶大なのに「白塗り、地味だな。ツヤなしだし」とか思えてくる。そのギャップもまた面白くて(笑)。屏風に波のような光を当てたり、日本的な要素が良い按配で入っているし、また麿さんのお茶目っぷりが際立った作品でちょっと卑怯だなと思った。ごめん、完全に脱線だ。でも「あうるの街の夏まつり」の前に、田村君とは話したいことがいっぱいあって、まだ脱線するかも(笑)。 田村:いえ、楽しんでいただけたようで嬉しいです。 近藤:この前、ラジオ番組に出る機会があって、そこでパーソナリティの山田まりやさんと年齢の話をしたら、「近藤さんそんなに若かったんですね。麿さんと同じくらいかと思ってました」って、まだ僕ギリギリ40代なのに!(笑)。でも改めて考えてみたら、麿さんと大駱駝艦はダンスカンパニーとしては大先輩だけれど、こういうどこか男っぽい、密な集団性のカンパニーは、コンドルズも含めて他にあまりないんだな、と思ったんですよ。だから山田さんも、麿さんと僕をなんとなく近く感じてくれたのかな、と。 田村:聞いています。その時、僕はいなかったんですが、笠井叡さん(麿氏と同世代の舞踏家、振付家。天使館主宰)や良平さんなど錚々たるメンバーが参加した伝説のWSだと。 近藤:ナジの作品を、偶然フランスの郊外で観たことがあるんだけど、サーカス学校の生徒たちとつくったものでね。鉢植えが置いてあるような壁を、普通に歩いていた人が不意にピョーンと飛び越えていったりする。サーカス的な演出もショウアップする装飾もないのに、見世物として成り立っている不思議な作品だったんだ。「こんなヘンなことを考えるのってどんな人かな?」と思って、WSも受けたんだけど。 田村:ナジのようなつくり方が僕は初めてで、例えば「象が溶けて蟻になる」というお題をポンと出してただ「やってごらん」と言うんです。場合によっては何人でとか、誰とつくれとかの指示もない。それで見せて良ければ「それやろう」と。面白いことをするとナジが頭を抱えながら「クックックックッ」と静かに含み笑いするんですが、「これがフランス流の褒め方なのかな」と勝手に想像して、その様子が楽しくて、とにかくナジを笑わせたら勝ち、みたいに思って踊ってました(笑)。 近藤:僕はこだわりがなさ過ぎるくらいなので、思いついたら「ヨシ!」とばかりに、動きや振付はたくさん用意するようにしているかな。「春」とか「はぐらかす」みたいに言葉がイメージのもととなる場合もあれば、音楽主導のときもあるし、モチーフはその時々でバラバラ。『にゅ〜盆踊り』のように、みんなで踊りながら「見知らぬ人同士が繋がる、今はいないご先祖様と繋がる」という、明確なイメージや目的があるつくり方は逆に珍しくて、だから面白かったんだけど。 田村:振りは厳密に決まっているんですか? 近藤:意外かも知れないけれど、コンドルズの作品は、ほぼ全編振りが決まっているんですよ。コント回りとかもアドリブのように見えて、ほぼ振付があってあまり自由な振る舞いは舞台上にない。なぜかというと、うちは野放しにしておくと「イエ〜イ!」みたいにイイ気になったり調子に乗ったりするメンバーが多いので、振付で縛ってようやくちょうどよくなるんだ(田村笑)。それに、いくら振付けても舞台上では、踊れる踊れないも含めた個人差が激しい人たちだから、結局は自由に見えちゃうんだよね(笑)。 田村:面白いですねぇ。麿さんの振付は大胆なんですが、最終的に非常に緻密になっていきます。 近藤:大駱駝艦は振りが細かいうえに、作品の密度も高い。「キュッと動いて、動いて、フッと緩める」とか、すごくそろっていて見て気持ちいいし、普通のユニゾン(同じ振りを集団で踊る)とは絶対に違う。あと、きっかけを声や息「シュッ」と吐いて出したりするでしょ? あれが独特で超面白い。 田村:きっかけ、あれは下手なヤツが出すと気持ち悪いし動けないんですよ。後輩にきっかけのダメ出しもしますから、「あそこは“アァァァ!”じゃなくて“ウッ”だろ!」とか(笑)。全員の間を合わしてあげる感じで出さないと、踊りの質がバラバラになってしまうんです。 近藤:冷静でないと出せないよね、きっかけ専門のWSとかあれば面白いのに(笑)。 ――大駱駝艦もコンドルズも、独自の方法論や思考、身体性を確立しているから、演劇や映像など外部のメディアや、他ジャンルのクリエイターから求められる人材を輩出しているのでしょうね。 近藤:確かに、「生きたメソッド」を持っているのかも知れない。ウチは、見え方はバラバラだけど。 |
 |
――田村さんは「芸術家と子どもたち」など、こどもに向けたWSなどの活動にも積極的ですよね。 田村:はい、地域創造の現代ダンス活性化事業などにも参加させて頂いたり、いろんなことをやらせてもらっています。2週間後には静岡に行くんですが、そこは3度目で、地元の赤石太鼓という和太鼓のチームとの共同創作。今回は皆さん演奏だけでなく「白塗りして踊りたい」と言っているので、今回はそのような作品にしようかな、と。 近藤:こどもたちにも白塗りしたことはあるの? 田村:顔だけ塗ったりはします。白塗りは仮面のような効果があるので、それまで引っ込み思案だったこどもが、塗ったら急に積極的に踊り出したりとか、「個」を消すことで「個」が出せるという、興味深いことが色々起こるんです。僕自身、稽古で塗らずに踊っていて、突然変なスイッチが入った瞬間、ものすごく恥ずかしくなって、気づいたら顔が真っ赤になってたりということもあります(笑)。 近藤:化粧にも同じ効果があるんだろうけれど、白塗りまでいくと自分の思わぬところに目覚め、解放できるのかも知れないね。僕でさえ、冬、たまにマスクをしたりすると、他人と視線が合いにくくなって、どこか心地いい感じがするもの。普段は自分を「人とは視線をちゃんと合わせて、明るく振舞いましょうね近藤君」と(笑)たきつけているから、余計気が抜けるのかも知れないけれど。 ――近藤さんも、一般の方とのWSの機会が多いかと思います。 近藤:そうですね。バレエやダンスの経験があるか、どのくらいやる気があるか、とか集まった人たちによって、僕はやることが違いますね。長く、いろいろと話すこともあれば、いきなり身体を動かす場合もあるし。 田村:僕らの踊りは、“農作業する農民の姿”とか“焼き鳥屋が焼き鳥焼く姿”とかなんだって踊りだと考えますから、間口はかなり広いと思います。僕は、リズムに乗って軽快に踊るようなことはできないし教えられないから、「今の、みんなが話を聞いているその姿がもう踊りなんだよ」ということから始めたりします。それに身体を動かしたり、踊りの話しをするだけじゃなく、僕が麿さんと大駱駝艦から学んだ、「何だって表現なんだ」とか、「こんなことも表現なんだ」ということを伝えたい。こどもの場合、「こんなことをいつも考えて生きている人たちがいて、こういう生き方だってあるんだよ」という話をすることも多いです。 近藤:いいねぇ、貴重な経験ですよ、それは充分に。 |
――今夏、あうるすぽっとでは、おとなとこどもが一緒に楽しめる「夏まつり」を実施します。近藤さんとコンドルズは恒例の『にゅ〜盆踊り』で参戦。田村さんには大駱駝艦メンバーと新作『はだかの王様』を振付・演出・出演していただきます。 近藤:面白そー! 普段から半裸で踊っている大駱駝艦のメンバーでつくる『はだかの王様』って、カンペキな企画じゃないですか(笑)。 田村:確かに(笑)。「ないものをあるものとして考える」とか、またその逆のことも、日本人の発想には色濃くあるものだと僕は思っていて。神様でも妖怪でも、普段目に見えない存在を確実に感じてきた。例えば、日本の音楽の場合、音がない「間」は単なる休符ではなくて、そこにものすごく重要なものがたくさん詰まっているように感じます。 近藤:なるほどね。 田村:そもそも白塗りにしていれば、どんな服だって着ているようにも見せられる。だから逆に、「ない」ということを見せるために、何をどう演出するかが課題でしょうか。あとはこどもたちの価値観や感性を想像して楽しみたいです。赤ちゃんてよく、同じ所を指差して手を振ったりするじゃないですか。僕らには見えない「何か」を見ているんだと思うんですけど、その点ではこどもたちのほうが「見えるもの」が多いと思いますからね。 近藤:そうかも知れないね。そうか、白塗りしてやるんだね。 田村:ええ、「こども向けだから白塗りしない」というのはおかしい気がするので。なかにはコワがって泣く子もいるかも知れないですけど(笑)、まぁ相当興味深く思わせるような何かを準備しないと、と覚悟はしています。あの王様、僕にはちっとも悪者に見えない。むしろ幸せだったんじゃないかと思うんですよね。こどもたちはどう感じるのでしょうか。 近藤:うん、切り口から面白い。楽しみだね。 |
 |
|
――『にゅ〜盆踊り』も今年で9回目。昨夏はのべ5,500人という多くの方が参加してくださり、豊島区周辺の夏の行事として定着しつつあると思います。 近藤:本当に有り難いことですよ。普通、ダンス作品をつくっても流れてしまうというか、やってもやっても「新作を」と望まれる、つらいループになりがちなんですよ。次の創作の糧にはなっても、作品が世の中の人にあまり残らないというか。でも「盆踊り」という演目は、その名がついただけで季節の行事として世の中に刻まれるというか、廃れない感じがして。実際、『にゅ〜盆踊り』も「夏が来ると毎年踊るもの」と習慣にしてくれた人がたくさんいたから、こうして続いてきたわけだし。自分でつくったものが、多くの人に共有され、しかも年を重ねて踊り続けてもらえる。そこに自分も参加できるのが非常に新鮮だし、作品が根づくことには大きな喜びがあるよね。 ――確かに。しかも年々参加者が増えていますから。 近藤:盆踊りって、天上か地下かは分からないけれど、亡くなった人、ご先祖様とかと踊りで繋がることでもあるでしょう? あの“繋がる感じ”も、踊りのルーツに近いものに僕には思える。その結果、踊りが「身体の記憶」になっていくんじゃないかな。もう、僕とは関係なく『にゅ〜盆踊り』は続いていく気がする。たとえば僕が「やめようかな」と思っても、危篤状態でも、みんなはきっと関係なくやろうとするよね(笑)。 ――踊りの活気で、近藤さんのほうが生死の淵から呼び戻されるのでは? 近藤:ありそうだねぇ(笑)。でも、そのくらいに盛り上がれば言うことなしでしょ。こどもたちのWSもね、どんな切り口や手法で始めても、上手くいくWSはこどもたちが勝手に遊び始める瞬間があるんですよ。僕の意図なんか関係なく、盛り上がり過ぎるほどになって、それをちょっと止める、くらいのときが一番良いWSだと思う。たがが外れるくらいはしゃいだあと、キュッと戻す。それがこどもたちと一緒に楽しめる作品や、WSなのかなと僕は思っているんだけど。 田村:僕も、今近藤さんが仰ったことと根本は変わらない考え方で、WSなどはやっています。舞踏の考えでは重要なことが、こどもにとっては一見退屈、ということもあるんです。「止まり続ける」とか「ゆっくり動く」というのは、こどもたちにとってはなかなか難しいですし。でもその面白さが伝わって、一度夢中になると、こどもたちは僕らでは絶対に考えつかない動きや表現を、不意にやって見せてくれる。その面白い出会いは、結果、僕にとってもすごく良い刺激になるんですよね。 近藤:経験の少ないこどもたちは、感情や動きを「記号」で処理しないから、「哀しい、楽しい、可笑しい」などの感情も、本当に独自の表現にしてしまう。あれは、おとなには真似できない。今年の夏、こどもたちがそんな楽しい時間を、あうるすぽっとでたくさん体験できるといいね。 田村:ええ、その手伝いを作品でできたらいいな、と思っています。 取材・文:尾上そら 写真:市来朋久 |
| INFORMATION |
|---|
『あうるの街の夏まつり』
あうるすぽっとでは、この夏「家族で楽しめる作品」を |