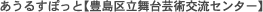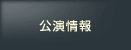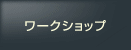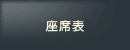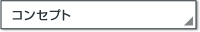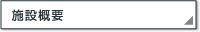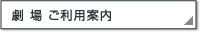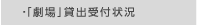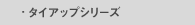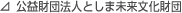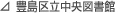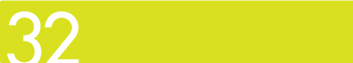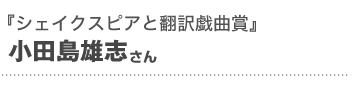トピックス・インタビュー32
|
世代もカラーもさまざまなアーティストが、劇聖シェイクスピアに挑んできた「あうるすぽっと シェイクスピア・フェスティバル2014」。力作に彩られた2014年度の締めくくりにふさわしいゲストとしてお招きしたのは、シェイクスピア全37戯曲を翻訳された小田島雄志さんです。翻訳家、演劇評論家として現役で仕事を続けながら、自身の名を冠した「小田島雄志・翻訳戯曲賞」で後進へのエールも贈る小田島さんに、多彩な人脈に彩られたシェイクスピアと演劇をめぐる若き日の挑戦から、日本におけるシェイクスピア上演の現状まで幅広く語っていただきました。
 |
――今年度は「あうるすぽっと シェイクスピア・フェスティバル2014」に関連したゲストを通年ご紹介してきました。第一回目に文学座の演出家・鵜山仁さん、高瀬久男さんが登場され、「文学座でのシェイクスピア上演は小田島先生の翻訳とともにあった」と話されたことが、印象深く残っています。 小田島:文学座では僕の前に、福田恆存さん訳の『ハムレット』ほか何本か上演しているんですよ。 ――入念な計画ですね。 小田島:それだけシェイクスピアがやりたかったし、翻訳の立場からもどんどん意見を言っていかなければと思っていたんです。当時、翻訳家は稽古初日にも呼んでもらえないなど、まだカンパニー・スタッフの一員として認められていないような状況があった。そのときからの ――出口さんの後の活躍を考えると、早すぎる結論ですね。 小田島:ところが辞めた翌年、文学座から電話があって「劇団でシェイクスピア・フェスティバルをやりたい。演目は『ハムレット』『ロミオとジュリエット』『トロイラスとクレシダ』を選んだので新訳をお願いします」と言ってきた。シェイクスピアをやりたくて文学座に入ったのに、辞表を出したあと1年足らずで同じ劇団からシェイクスピアの翻訳が仕事でくるなんて皮肉だよね。まぁ嬉しかったんだけど。 ――それが鵜山さんたちの仰った文学座での小田島訳シェイクスピアの先鞭になったのですね。どのような内容になったのでしょう。 小田島:『トロイラス〜』にはケンブリッジを出たジェフリー・リーヴスという若い演出家をイギリスから呼んだほか、『ハムレット』は出口演出、『ロミオ〜』は木村光一が演出することになりました。アトリエを「田」の字型に分けて一辺を舞台、残る三辺を客席にして、装置はこれをベースに3作それぞれにアレンジした。ハムレットを演じた江守徹、ジュリエットの太地喜和子など、記憶に残る芝居をしてくれましたよ。 |
|
――アトリエの熱気が感じられるようです。 小田島:実際、観客にもよくウケたんです。『ハムレット』でも、ちょっとしたことでドッと笑ってくれたりして。それを見て、ある劇評家は「シェイクスピアを侮辱するものだ」なんて書いていたけれど、僕は、泣いたり笑ったりしながら観てこそのシェイクスピアだと思っていたから、すぐさま反論しました。 ――まだ、シェイクスピアを有難いもの、冒しがたいものとしてあがめるような風潮が残っていたのですね。当時から今に続く小田島先生の活動が、シェイクスピアを自由に上演できる環境を整えてくださったのでしょう。 小田島:笑うどころか、「くしゃみもしちゃいかん」みたいなことを言う連中がいたんですよ、当時は。 だから、僕の訳したシェイクスピアの全集が出たとき、故井上ひさしが「今までシェイクスピアは教養として読まれていた。この訳が出てからは娯楽として読まれるようになるだろう」というようなことを言ってくれて、それは本当に嬉しかった。もう一人感謝しなければいけないのは、やはり出口ですね。 ――出口さんは小田島先生の訳で、シェイクスピア全37作を演出・上演された方。高瀬さんは若いころ、出口さんの演出の手伝いなどされていたとうかがいました。 小田島:文学座をやめた出口は3年ほど劇団四季にいたあと、75年に自身でシェイクスピア・シアターを立ち上げる。劇団を旗揚げした時点では、公演の見込みはまったくなかったんです。それが色々と僕の伝手で縁が繋がり、渋谷にあった小劇場ジァンジァンの支配人に出口の劇団を紹介することになった。最初は、劇場が演目の都合で空く年4回、公演をしないかという話だったんだけど、シェイクスピア・シアターの稽古を見にきた支配人が、それこそ武者震いのように震え出してしまって。最初の演目は『十二夜』でしたね。その場で「年4回なんて言わずに毎月やりましょう!」と言い、シェイクスピア全作上演へと話が膨らんでいったんです。構想としては月に5日間の公演で、1年の半分6回分は新作、もう半分は再演と。結果、6年間で37本やってしまった。 ――ジァンジァンに長蛇の列ができた、という盛況ぶりの「伝説」は聞いたことがあります。 小田島:席数110くらいの小劇場なのに、200人入ることも珍しくありませんでした。酸欠で倒れるお客さんも毎回出るような状態で。 ――小田島先生や出口さんがシェイクスピアへの門戸を広く開いてくださったお陰で、色々な出自、世代の演出家がシェイクスピアにチャレンジできる、「あうるすぽっと シェイクスピア・フェスティバル2014」のような企画も成立する土壌ができたのだと思います。ますます上演機会が増えている感のあるシェイクスピアですが、日本の現状を小田島先生はどのように見ていらっしゃるのでしょうか。 小田島:ちょっと話が回り道をしますが……僕の若いころ、翻訳劇の主流といえば古典はシェイクスピアとモリエール、近代劇はチェーホフとイプセン、アメリカの現代劇ならテネシー・ウィリアムズとアーサー・ミラーだった。これらがほぼ均等に上演されていて、僕らはそれを観て育ったのだけれど、この6人の劇作家の作品を、時代とは別に二つに分けられることに僕はあとから気づいた。グループ分けは「シェイクスピアとチェーホフとテネシー・ウィリアムス」で、もう一方は「モリエールとイプセンとアーサー・ミラー」。前者の戯曲は可塑性が高く、演出家の意図を加えて好きな形で上演しやすい。人物にしろ演劇形態にしろ世界観にしろ柔軟なんです。ところが「モリエール、イプセン、アーサー・ミラー」になると、戯曲の原型がきちっと書かれ過ぎていて、つくり手が自分のイメージをプラスして作りにくい。 ――なるほど、とても分かりやすい分類です。 小田島:だからロンドンでいうフリンジ、ブロードウェイならばオフやオフオフなど小劇場では前者の戯曲が人気を集めた。材料や素材としての魅力が大きいんですよね。つまり、自分の言いたいことや表現したいことがちゃんとあれば、いくらでも面白い舞台ができるけれど、逆にそこが弱いと手こずることになる。シェイクスピアはだから、つくり手の内面にあるものをあからさまにする戯曲だと思います。 ――シェイクスピアは演出や解釈に目が行くと言われますが、それ以前に、つくり手が創作に向き合う精神性や、その人の本質があぶり出されてしまうのですね。 小田島:もうひとつ、20世紀の終わりから21世紀にかけてくらいからずっと気にかかっているのが「言葉」の問題なんです。僕ら旧制高校に通った世代の人間は、若いうちに必ずといっていいほど文学に傾倒していた。小説や戯曲ももちろん読んだけれど、一番影響を受けたのは詩人たちの言葉。僕が熱中したのは、高校時代は中原中也で、大学に入ってからはT・S・エリオットが基礎を築いたイギリスの現代詩。特に大学では詩の同人誌を出すほどのめり込んで、一時は「現代日本詩人書録」に名前と住所が載っていたほど(笑)。 ――シェイクスピアを手がける演劇人だけでなく、観客のさらに豊かな観劇のためにもなるお話だと思います。最後に、08年に立ち上げた小田島雄志翻訳戯曲賞について、お話を伺えますでしょうか。 小田島:本当にささやかな賞ですが、戯曲の翻訳に贈られる前身の湯浅芳子賞が終わったとき、翻訳家の仕事に光を当てるチャンスを減らすべきではないと僕自身が強く思ったんです。僕が芝居の翻訳家として仕事を始めたころは、まだ翻訳家をスタッフの一人として認める環境がなかった。本読みの初日に呼ばれなかったり、クレジットに名前が掲載されていなかったりすることがザラだったんです。もちろん、翻訳家側にも「覚悟」は必要だと思います。だからこの賞があることで、翻訳家の仕事と存在をちゃんと評価し、世に訴えると同時に、翻訳家自身にも覚悟を促すことになれば良いと僕は思っているんです。そのために女房には、「年1回、これだけのお金を好きに使わせてください」と、ちゃんと許可ももらったんですよ(笑)。 ――奥様の許可がいただけて良かったです(笑)。 小田島:こういうところは、ちゃんとしないとね。公演パンフレットなどを読み、翻訳家のプロフィールに賞の名が書いてあるのを見ると僕も嬉しいし、続ける甲斐もある。演劇関係だけでなく、翻訳の仕事の認知や評価はまだまだ世間では低いと僕は思っているんです。そこに一石投じられるよう、続けられる限りは頑張りたいと思っています。
|
 |