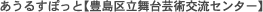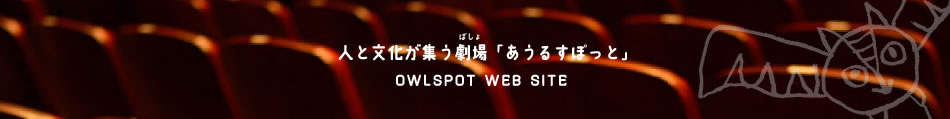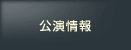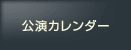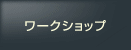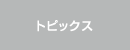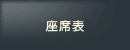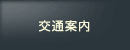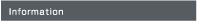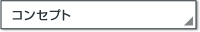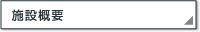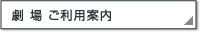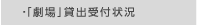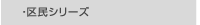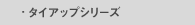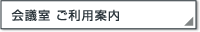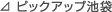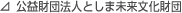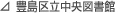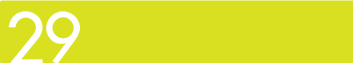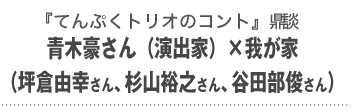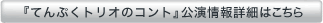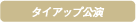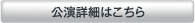トピックス・インタビュー29
|
日本を代表する劇作家、故井上ひさしが自身の戯曲を上演するため旗揚げした「こまつ座」。2014年は、こまつ座が30周年を迎えます。その節目の企画が『てんぷくトリオのコント』です。活動の初期にテレビの構成作家として活躍した井上ひさしが、その「笑い」のセンスを研鑽したのが三波伸介、戸塚睦夫、伊東四朗からなる「てんぷくトリオ」へのコント台本執筆だと言われています。残された名コントに演出・青木豪と我が家の3人、監修・ラサール石井が新たな生命を吹き込む挑戦的な舞台。6月、あうるすぽっとを笑いの風が吹き抜けます。
 |
――青木さんは我が家さん所属のワタナベエンターテインメントさんとは、シェイクスピア作品の上演などでご一緒されているのですよね。 青木:はい、去年の『十二夜』には坪倉さんにも出演していただいて。杉山さんと谷田部さんには、その公演中にポスト・パフォーマンストークにゲスト出演してくださった時に初めてお会いしたんですよね。 坪倉:トークが終わった後、豪さんが「素晴らしかった!」と手放しで褒めてくださったんですが、その時初めて心から認めてもらえたと思いました。結局演技じゃなくトークか、と(笑)。 青木:いやいや、坪倉さんのお芝居も良かったんですが、毎日のようにあったトークが割りとユルイ感じだったので(笑)。そこへ行くと、お三方はさすがのテンポで、笑いもドカンドカン起きてたじゃないですか。客演のミッキー・カーチスさんが思わず飛び入り参加したくらいに盛り上がって。僕はコントのことはあまり詳しくないので、今回は我が家さんのお力を存分に貸していただかないと。 坪倉:『十二夜』で受けた豪さんの演出は、本当に人をよく見て、その人の個性を引き出してくださるものだったんです。今まで一緒にやってきたものの、僕はいまだに杉山と谷田部の良さがまったく分からないので、今回はきっと、僕に分かるように二人の良さを引き出してくださると思っています(笑)。 杉山:10年以上一緒にやってきて、お互いの良さが分からないのは問題だろう!(笑)。 ――普段自分たちでネタを作り、演出も含めて上演する我が家さんにとって、井上ひさしさんのコント台本があり、しかも演出の青木さんや監修のラサール石井さんがいらっしゃる創作は、初めての取り組みですよね? 坪倉:今まで経験のないことですね、お芝居とも違うし。まして、大先輩のてんぷくトリオさんに書かれたネタですから、自分たちの色がなくてもいけないし、真似しようと思ってできるものでもないし。 谷田部:てんぷくトリオさんの動画なども、ほとんど残っていないんですよね。でも、ネタにある時代感のようなものは、再現できたらいいなと思っているんですが。 杉山:動画はなくて良かったんじゃない? 変に先入観があるより、目の前の台詞通りにイメージして作っていくほうが自由度が高いと思う。結構昔の言葉、今の日常では使わないような言葉も多いので、どう伝えていくかが課題になりそうですね。 ――皆さん、てんぷくトリオの全盛期以降のお生まれですよね。 青木:僕が物心ついたときは、もう戸塚さんが亡くなっていて。三波さんと伊東さんがそれぞれテレビで活躍していた頃です。お三方は伊東さんとご一緒にお仕事されたことは? 三人:ありません。 杉山:もし伊東さんがこの舞台をご覧になっても、恥ずかしくないものにしないと、と思いますよね。 谷田部:伊東さんが出て下されば良いのですが…? 杉山:自分らのハードルを相当上げることになるよ(笑)。 谷田部:稽古中にいらして、裏ワザとか教えてくださったらいいのになぁ(笑)。 ――井上さんが書かれたコント台本はいかがでした? 坪倉:現代にも通じるところが、たくさんあると思いました。それを今のお客様にどう伝えるか、が問題で。 杉山:やるからには何らかの形で自分たちのモノにしたいじゃないですか、演じ手が違えば少しずつ違いは出てくるはずですし。そういうことを大事にしながら、笑えるところは絶対に外さないようにやりたいですよね。 青木:僕も、普遍的な笑いが書かれている台本だと思いました。だからこそ、台本を忠実に再現するべきか、「今やっても普遍的に面白いゾ」と新しい演出を加えるべきかが悩ましい。そこはラサールさんや、我が家さんとしっかり話し合いながら方向性を決めたいです。井上さんのインタビューに、てんぷくトリオさんとの仕事について「自分が書いたオチが弱いと、てんぷくさんたちが大きめに決めて補ってくれた。そのことで自分の腕も磨かれた」という記述があって。僕もこの企画できっと、腕を磨かせてもらえるのでは、と思っているんです。 谷田部:そこは僕らも同じで、すごく鍛えていただける機会だと思っています。ネタによっては、普段の僕らのポジションとは違う役割をやってもいいでしょうし。それに、お客様の層も、きっといつもとは違いますよね? いつもは若い子たちが中心ですが、今回はかなり年齢層が幅広いんじゃないかと思っていて。 青木:確かに年配のお客様も観に来てくださりそうですね。でも、ゆっくりやると眠くなる方も多そう(笑)。だから敢えて速めにやって、食いついていただくのもいいんじゃないかと個人的には思っています。 |
 |
|
――青木さんから観た「我が家」の魅力はどういうものですか? 青木:やはり「間」が非常に良いですよね。淡々とやりつつ、ツボは外さないというか。 杉山:それは非常に嬉しいです。 坪倉:いや、でも芝居の稽古場での青木さんは、キビしいというかコワい一面を持っているのを僕は知っているので、僕らにもドンドン突っ込んで演出していただきたいです。良いものを創るためには当たり前のことですから。 ――でも確かに、我が家さんのネタは言葉や振りがきれいに渡されていく感じが、演劇的にも見えました。 坪倉:そこは、天性のものなんで(杉山、谷田部笑)。 杉山:もう天狗発言ですよ! 坪倉:杉山さんよく言うじゃないですか、「天性のものだ」って。 杉山:俺は言ってない! なすりつけんな!! まぁ、「間」はコントをやる者としては大事にしている部分ですから、ネタをつくりながらも三人でよく話し合いますね。 坪倉:かなり感覚的なものですけれど。確かに昔の映像を見ると「下手だな」「焦ってるな」と思う「間」も多いですし。 青木:ネタをつくるときは、誰か一人が演出的な立場になるんですか? 坪倉:おのおの、客観的に見て意見を言い合う感じですね。意見が2対1になれば2のほうに決める、みたいな。そこは多数決です。 谷田部:その点、トリオは便利ですね(笑)。 坪倉:最初ネタは僕一人でつくっていたんですが、コント番組が始まって、週に一本ペースで作らなければいけなくなってからが大変で、「3人でつくろう」と。そのほうが覚えやすいですしね、3人でつくりながらやっていくと、「書いたものを覚える」という別作業ではなく、ひと続きでできるので。 杉山:そうね。イケると思ったものは、どんどん先が見えてくる。 谷田部:逆にテレビ局の楽屋で15時間くらい粘って、何も思いつかなかったこともありましたよね。 杉山:そうそう、いくつかネタは出てきたんだけど、その先が面白くならない。 坪倉:尺にして1分くらいはできるんだけどね。15時間中、12時間くらい黙ってました(笑)、話しているのは5分の1。 杉山:「今日は帰ろう」って言う勇気がなかったんだよね、良いものできるわけないのに。 谷田部:切羽詰まったとき、ようやく真剣に考え出すから。サボりたいんですよ、みんな(笑)。 青木:でも、それよく分かります。僕も15〜30分くらいの短編を書くとき、一日で書けないものは絶対につまらない、ひと筆書きみたいに一気にバーっと行けないと。3日くらいかかった30分は絶対に面白くない。こねくり回しただけなんですよね、結果的に。コントのほうが集約しているぶん、戯曲より一ネタずつのテンションも高いから、出来不出来は顕著でしょうね。 |
 |
|
――青木さんは、ご自身の作品の中で「笑い」をどう位置づけているのでしょう。 青木:「笑い」ですか……いや、必要なときに入れている、くらいなんですが。 坪倉:僕は青木さんの演出を受けたとき、「こんな笑いの作り方があるのか」と目からウロコが落ちました。正直「コレが笑いになるの?」と思うような場面もあったんですが、実際やってみるとちゃんと客席から笑いが起きる。正直、舞台を相方に観られるのは不安だったんですが、色んなジャンルの笑いが作品で見せられたし、演出家である豪さんのなかに、そういう多種類の笑いがあるんだと僕は思いました。 青木:「笑い」ってやっぱりコワイんですよ、センスを問われるものじゃないですか。音楽と同じで「コイツこんなの聴いてんだ」みたいに他人から思われて、そのことで疎遠になったり親しくなったりするような。飲み屋で近くに座るかどうかを左右するみたいな(笑)。 杉山:確かに、今では使えないような言葉をサラッと使って笑いにしている。 青木:こういうことを笑いにできた時代はいいな、と思えるんです。 ――今は過剰な自主規制の風潮が、マスメディアにありますしね。 坪倉:その点は、僕らは攻めてるほうじゃないですか? はじめはダメだった下ネタが、後々OKになった番組とかありますから。 青木:そのネタが好きなプロデューサーさんがいたんでしょうね(笑)。 坪倉:テレビなどのメディアに比べると、舞台はその点で自由度が高いと思う。多少タブー視されているネタや言葉でも、笑いになればいい。スベったら終わりですけどね(笑)。 青木:そこが難しいところですね。 杉山:最初のほうのネタに、「死刑囚と電気ショック」を扱ったのがあるじゃないですか。あれを笑いにできた、てんぷくトリオさんの技量やキャラクターもスゴいと思います。 ――井上さんは戯曲でも社会の底辺で生きる人の実態、差別などについて果敢に書き続けた作家です。 青木:そう、デフォルメされてはいても現実に、この社会に起こっていることなんですよ。それは、表現に取り入れてしかるべきだし、むしろ無いことのように目を逸らすほうが気持ち悪い。 坪倉:全部笑いにしてしまえばいいんです。お笑いは世の中において、そういう役割も持っていると僕は思います。 ――デビューから今日まで、我が家のお三方は「笑い」の定義や価値観など変わったと思われますか? 坪倉:基本の「たくさんのお客様に笑っていただきたい」という気持ちなどは変わりませんが、細かい技術や志向などは変化しますね。 杉山:僕も基本は変わらないけれど、改めて「お笑いは難しい」とは思ってきていますね。先輩方に比べてまだまだ自分たちは頑張りが足りないと思うし、明石家さんまさんとか、わざわざ笑わせているというよりは、普通にしていて面白いじゃないですか。「自然にいて面白い人」になれたらいいですよね。 谷田部:僕はまあセミプロみたいなものなんで、なんとも言えないんですけど……。 杉山:セミプロはちょっと言いすぎだ、アマチュアにしておいたほうが楽になれるゾ(笑)。 谷田部:すみません、出過ぎました(笑)。 坪倉:自分を良いように言うなよ、何がセミプロだ!(笑)。 谷田部:すみません……でもネタづくりとか、若い頃はだいぶ世界観が飛んだことを考えていたけれど、段々、皆が共感できることを入り口にしたほうが笑いが取りやすい、ということのには気づいてきました。アマチュアとして(笑)。 坪倉:確かに最初は言葉で笑わそうとしていたところから、「人として笑わせたい」というか、「この人ならこういう感情になるはず」とか、心の動きや変化で笑わせたいと最近は思っていますね。 谷田部:「こういう人はこう動く、こう動いたら面白いだろう」という考え方ができるようになった、というか。 杉山:最初の頃は店員役でも店員になりきっていなかったもんね。 ――演技にも通じますね。キャラクターが生きていないと面白くないし、生きていればどんどん笑いが生まれる。 坪倉:“狙ってる感”じゃなくて笑わせたいんです。「ボケました、はい、笑って」というのではなく。 谷田部:ボケてないけど笑いになるようなネタ、なるだけ自然なキャラクターで笑いを取ろうとしてますね、最近は。 青木:芝居も同じですよ。若いときは派手なネタがすきだけど、段々チェーホフとかに目覚めたりするような(笑)。 坪倉:そういう感覚は、去年豪さんの演出を受けたときすごく感じたんです。「笑いを作る場面でも“狙ってる感”は出さないように」とか。すごい勉強になって、我が家にも持って帰ろうと思いました。 青木:そういうお互いの共通点と違いを、井上さんのコントの中でどう活かせるか。ハードルは高いけれど、そのぶんやりがいも大きいですよね。 三人:僕らもすごく楽しみにしています!! |
 |
 |
| INFORMATION |
|---|
|