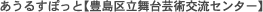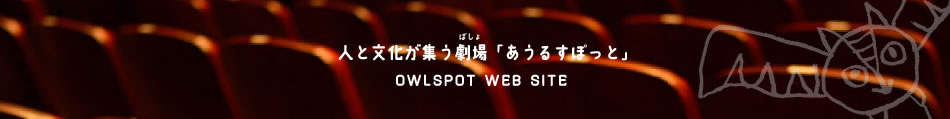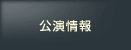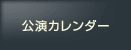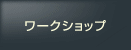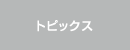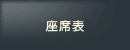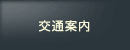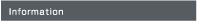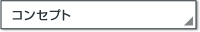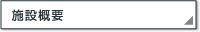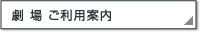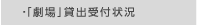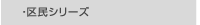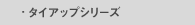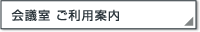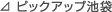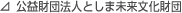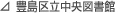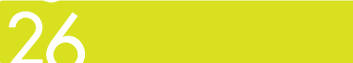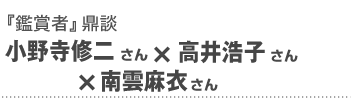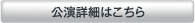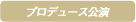トピックス・インタビュー26
|
あうるすぽっとでは2009年から3年間にわたり、小野寺修二さんと大塚ろう学校の生徒たちによるワークショップと、その成果を発表する公演を重ねてきました。ろう者の方々と舞台の時間を共にする経験から得たものは、クリエイターである小野寺さんにとって非常に大きな刺激になったとのこと。そこから見出した新たな創作の可能性を推し進める場として、この『鑑賞者』の企画が立ち上がりました。ダンサー、俳優、舞踏家5人に、ワークショップを経験したろう者お二人が加わるカンパニーが今、未知の大海へと滑り出します。
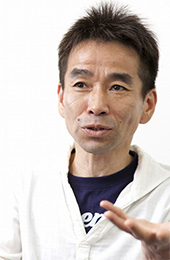 |
――小野寺さんとろうの方たちのワークショップ(以下WS)は09年、あうるすぽっとでの実施以前から始まったことなのですよね? 小野寺:はい、「水と油」というパフォーマンスシアターで活動していた頃に、この公演のスーパーバイザーであるミューズ・カンパニー(コミュニティ・アートの普及に尽力する団体)の伊地知裕子さんにお声がけいただいたんです。もう10年以上前でしょうか。「ろうの方に向けてWSをやってみませんか」と最初にうかがった時は、まだ障碍を持つ方と接する機会がほとんどなく、戸惑いました。ただ「水と油」の表現には「言葉を使わない」というルールを設けていた。そのことと、ろうの方の「言葉が聞こえない」という状況には、何かしら共有できるもの、あるいはろうの方たちの置かれた状況から僕らが学ぶことがあるのではないか、と思い至りまして。ならばWS以前に、まずただの人間同士としてお会いしたい、というお願いから始めさせていただきました。 ――私は10年の会を拝見しましたが、出演者の方たちが非常にのびのびと舞台を楽しんでいる姿が印象的でした。 小野寺:「劇場に足を踏み入れる」「舞台に立つ」という行為を、少し早めなくらいに子供たちに経験してもらうのは、僕ら創り手側の人間にとってもプラスだと思うんです。劇場に入った時のワクワク感、演劇や表現に触れることの刺激。学校の授業で舞台を観るのとはまた違った、本当の生の舞台の魅力を早くに知ってもらうことは、次の世代の観客と創り手の両方を育てることになる。その点で劇場上演を前提にしたあうるすぽっとでのWSは、非常に意義深いことだったと思います。 ――南雲さんが最初に小野寺さんのWSに参加したのは? 南雲:二年前です。小野寺さんの作品の映像を偶然ネット上で見つけたんですが、言葉がなくても身体の動きや表現だけで色々な風景、物語が見えてくることにとても興味が湧いて。で、小野寺さんのサイトを調べたらWSの募集があり、締切間近だったので急いで応募しました(笑)。 ――素晴らしい巡り合わせですね。 南雲:はい、良い偶然に恵まれました。全てが初めての経験でしたが、聞こえない私は普段から、「見る」ということに結構気負ってしまうんですね。見ている範囲も一般の方よりは広いし、周囲の動きに対しても敏感。そういう自分の行動を、小野寺さんのWSを受けることによって「他の人にはできないことが自分にはできる!」と自覚することができたんです。それは、とても嬉しい発見でした。 小野寺:南雲さんの話を聞いていると、訳もなく感銘を受けてしまうんですよ。一つ一つの言葉をじっくり聞いてしまう。こうして南雲さんと出会えたこと、その出会いが作品へと繋がっていること、心から嬉しく思います。 ――創り手を最も喜ばせる言葉を、南雲さんは今さりげなく口にされましたから。高井さんは、小野寺さんと今回初めてご一緒に創作されるんですよね? 高井:はい。でも以前から私、小野寺さんの作品のスゴいファンだったんです。「水と油」の頃から拝見していますし、そのうちうちの劇団(東京タンバリン)の公演を観に来てくださったあうるすぽっとのプロデューサーの方が、「小野寺さんと仕事をしてみればいい」とアドバイスしてくださって。 ――確かに東京タンバリンの作品では、場面や物語の説明とは一線を画した、フォーメーションのような動きや身体表現を演出に取り入れていますね。 高井:ええ、そこに関して「(小野寺さんに加わってもらえば)もっと動きが良くなるはずだ」という助言でした。だから今回のお話は非常に嬉しく光栄であると同時に、ものすごいプレッシャーにもなっていて。私一人だけ後ろに下がらぬよう、皆さんと同じ道を前に進んで行かなくては、と肝に銘じて参加させていただいています。 小野寺:ここ数年は、色んな劇作家の方と仕事をさせていただき、皆さんそれぞれに大きく違うと実感しています。違う個性に相対し、そのなかで僕の我がままをどれくらい理解してもらえるかは、もうある種の勝負ですよね。高井さんが普段書かれているものと僕の要求が、完全にリンクするわけはない。けれど一生懸命僕の我がままにつき合っていただきつつ、同時に少しずつ、高井さんの色や考え方を差し込んでいただくための隙間をつくるのも僕の仕事。安易なコラボレーションに逃げず、今はとにかく僕のなかにあるイメージを全部高井さんに託し、さらにはパフォーマーさんたちの全力のサポートを得て、本当のゼロから誰も観たことのない舞台を生み出したいと切実に思っています。 |
|
――稽古が始まる前段階から、既にアツい創作の時間が始まっているんですね。 小野寺:これ以上「言葉」について、それは作る過程において用いる「言葉」と、実際舞台上で発語する「言葉」の両方についてですが、立ち戻って考える機会はそうはないと思います。無自覚に言葉を使ってしまうと、動きの面でもストーリーの部分でも、ポロポロ抜け落ちてしまうものがある気がする。南雲さんともう一人、山田真樹君というろうの方に出演していただきますが、僕自身まだ気付いていない彼らへの思い込みは、気を付けないと平気で塗り込めてしまう傲慢さがありそうで、そのことは、自戒をこめて。それを損なわないための言葉や動きを、今必死に探している最中です。高井さんはそういう面倒な作業にも、嫌な顔をせずつき合って下さるので有難いです。本音はお嫌かもしれないけれど(笑)。 高井:(笑)いえいえ、それはありえません。 小野寺:それに、以前から作品を観ていてくださったことも心強い。僕の作業を外から見て、表にでる形を理解してくださっているので、ご自分から色々チャレンジしてくださるんです。むしろ今は、上手くイメージを伝え切れていない自分がイヤになります。 高井:いえ、話し合えば話し合うほど可能性は広がり、そのぶん、確信が持てないことも増えるんですが、それにしても私にとっては新しい取り組み。絶対、今後の創作の糧になると信じています。 ――南雲さんはプロの俳優やダンサーの方との共演について、どう感じていますか? 南雲:不安に思う気持ちより、嬉しさが優っています。プロの方たちのとても近いところにいますから、たくさんのことを吸収できると思うんです。自分の中でも「ヨッシャ!」と気合を入れています(笑)。もちろんプレッシャーが全くない訳ではありませんが、今回の舞台なら言葉を越えた何かが見つかるかもしれないし、小野寺さんを始めとしたプロの方たちと一緒に新しい挑戦ができるなんて滅多にないこと。お互いの良い刺激になれたら、と思っています。10年後、20年後も共演した方たちが私の名前を覚えていてくれたら嬉しいですよね。 ――スゴい、想像以上に大物です、南雲さん。 小野寺:でしょ(全員笑)。 南雲:そんなことないです、初めて舞台に立った時はきっと緊張もしていました。でも同じくらい嬉しくて、またやってみたいと思えたんです。社会の中での私はマイノリティ。「聴こえない」ためにどうしてもできないことがあり、それを可哀想だと言われたり、差別されたりもしますが、舞台上ではそういうことが一切なかった。きっと人種や言語も越えて、舞台に立っていれば皆、同じ扱いになる。そんな全てにおいて平等な世界では、「聴こえないこと」も特別アピールしたくないんです。むしろ「あの人本当に聴こえないの?」と思ってもらえたら嬉しい。私は、そういうことを求めています。 小野寺:僕が言わなければいけないことまで全部、南雲さんが言ってくれた感じです(笑)。 |
 |
|
――高井さんは09年に劇団で、ろうあの女性を中心とした『静かな爆』という作品を劇作・演出していらっしゃいますが、この作品に参加することになり、特別な感慨がおありでしたか? 高井:個人的には思うところもありましたが、小野寺さんが創ろうとしていらっしゃるものは、違う気がするんです。私の作品ではコミュニケーションの可否による区別・差別を描いていましたが、小野寺さんは今回、そういう「境界線」的なものが無い舞台を創ろうとしているのではないか、と。だから『静かな爆』を書いたのとは違う脳で考え、書かなければならないでしょうね。 ――稽古開始以前から、ここまでカンパニーの方に理解と協力を得られていることが素晴らしいと思います。 小野寺:今日ここにいない他の方たちも、僕が大きな信頼を寄せている魅力的な方ばかり。南雲さんや真樹君に是非紹介したいと思ったし、全員が二人から多くのものを受け取り、創作のために活かしてくれると思っています。 南雲:私、最近偶然に共演者の方の踊りを観る機会があって。「こんな方と踊れたらいいな」と思って、いただいた企画書を見たらお名前があってビックリしたんです! 大駱駝艦の小田直哉さん。 小野寺:分かる! 好きだろうなぁ、南雲さん。踊りには色々あるけれど、大駱駝艦の方たちはやはり特別。人間が内面に抱える「何か」が、いやらしくなく表現として出せるんですよ。フォルムや形も面白いし、技術的にも高い。そういうダンスや動き、身体性があることを、南雲さんたちだけでなく観に来てくださるすべての人に知って欲しいんです。 高井:この稽古場、是非うちの劇団員にも見学させたいです。
――確かに、創る過程からただならぬ気配が漂っています。 小野寺:『鑑賞者』というタイトルにしたのは、「見る」ことが全ての始まりであり、「創る」ことの起点になるという意味合いと、「見る」という行為がどういうものかを検証する意志の両方を込めてのこと。パフォーマー同士が互いを見る、観客がパフォーマーを見る、そしてパフォーマーも観客を見る。劇場では常に誰かが誰かを、誰かが何かを見ているんです。そのなかで見ることに長けている自覚のある南雲さんたちが、「意外に自分たちにも見えてないものがある」と気づくことになれば嬉しいし、今までとは異なる世界の見方を発見してくれたら尚嬉しい。その「気づき」はきっと、観客にも伝わること。諦めずに最後まで創作を突き詰めたいと思っています。 取材・文/尾上そら |
 |
 |
 |
小野寺修二 |
| INFORMATION |
|---|