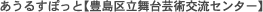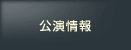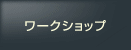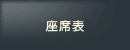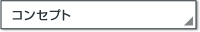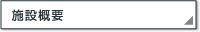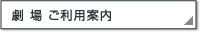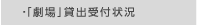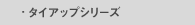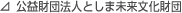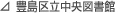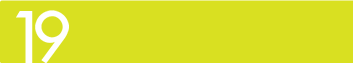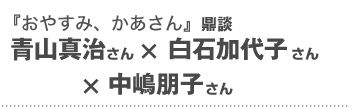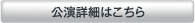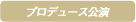トピックス・インタビュー19
|
娘は母親に自殺すると宣言し、母は娘を止めるため必死の説得に当たる。支え合うには、あまりに孤独過ぎる母と娘、その運命を大きく変える一夜。衝撃の設定と感動のラストで1983年のピュリッツァー賞を受賞したマーシャ・ノーマンの戯曲『おやすみ、かあさん』が、日本で11年ぶりに上演されます。演出は今春、舞台演出を初めて手がけた映画監督・青山真治さん、ママ役は初演に引き続き白石加代子さん、そして娘ジェシーを新たに演じるのは中嶋朋子さん。少人数ながら大きな成果が期待されるトリオに、創作の展望と抱負を伺いました。



|
――演劇、映画両方の愛好家にとって、非常に嬉しいコラボレーション企画が立ち上がったように思います。 青山:私のほうこそ、こんなにも演劇にお邪魔して良いものか、と恐縮しつつ、これほど素晴らしい女優の方々と仕事をさせて頂ける機会はそうそうありませんから、存分にやらせてもらおうと心は決めています。笹部プロデューサーにご紹介頂いたこの戯曲にも、惚れ込んでいますしね。 ――白石さんは11年前に演じた際の印象など、記憶に残ることはありますか? 白石:旅公演を随分たくさんしたことは漠然と覚えていますが……ダメね、過去のことはすぐ忘れちゃって(笑)。でも、私は長いこと抽象劇ばかりやっていたから、こういうリアリズム的なお芝居をやり慣れていなくて。その意味では苦労した作品でした。台詞の他に日常的な細々した動作をたくさん身体が覚えなきゃいけなくて。むしろ、物語の悲劇性より、色んなことが自分の頭に入らない悲劇性のほうが気になって仕方なかった(笑)。母と娘の日常が舞台上に溢れていて、つくづく「私にはリアリズムは向かないなあ」とか「芝居の日常性に殺される!」なんて思っていたの。 ――中嶋さんは戯曲を一読されていかがでした? 白石:(笑)初演は生まれてなかったでしょ? 中嶋:さすがにソレはないですよ! でも戯曲を最初に読んだときは、かなり震えました。凄い衝撃で、本当に「震える」としか言いようのない感覚だったんです。描かれているのは悲劇的な出来事ですが、それよりも私には作品に「光」のようなものが感じられて、「この光をどうしたら表現できるだろう?」と考えるだけで、興奮とワクワクがない交ぜになった感覚に囚われて。めったにない感覚だったから、嬉しくなってしまいました。 白石:やっぱり朋子ちゃんは澄んでいるのね。私とはちょっと感性が違うのよ。 中嶋:加代ちゃんたら、何言ってるんですか! 白石:もちろん嬉しいのよ、今まで共演こそあれガップリ四つで朋子ちゃんと芝居をする機会はなかったから。 中嶋:ええ、『グリークス』では敵同士、殺し・殺される関係で。 白石:夫である平幹二郎さんとその愛人の朋子ちゃんを、大きな斧で私が殺すという設定なの。あの作品は全部で9時間あるから待ち時間も多くて。私は間が空くとすぐ、朋子ちゃんのそばへ行っていたの。朋子ちゃんの佇まいが好きだったのよね。 中嶋:本当に仲良くして頂いて。私のほうも楽屋へ「加代ちゃん♪」なんて遊びに訪ねてましたね。 青山:僕は、お二人の仲良しに水を差さないよう気をつけないといけないですね(笑)。 |
|
――青山さんが初めて舞台演出を手がけた『グレンギャリー・グレン・ロス』も、前半は二人芝居の連続のような不思議な構成でしたが。 青山:演劇であれ映画であれ、劇を成立させる、会話を成立させるための一番シンプルで大切なことは「声」だと思うんです。それを聞かせることが一番大事だと僕は思っている。声・言葉・台詞というものが、お客様にどのくらい強く届くか。それを考える時、「二人」という単位は非常に強いと思います。 白石:そこまで仰られると不安ねぇ(笑)。でも、私がママを演じるこの作品の娘役に、朋子ちゃんを配して頂けるなんて想像もしていなかったの。だから最初に聞いた時は、「この話が潰れませんように」と祈ったほど。私はいつもキャスティングにはノータッチで、決まったことを「やらせていただきます」と言うだけだったから。たかが女優ですからね。 青山・中嶋:「餌食」ですか! 白石:そう! 願っていれば叶う、待っていれば良いこともある、という絶好の証明よね。 中嶋:フフフ「餌食」ですか、でも嬉しい。良い蜘蛛の糸にかかったんじゃないかな、私(笑)。 青山:いいなぁ、このぶつかり合い。気持ちが良い限りです(笑)。僕は、お二人にやって頂けるならセットのないリーディングでも、原っぱでもいいと言っていたくらいなので。 白石:いいじゃない、野外だって。 中嶋:素敵ですよね。 |
   |
|
――白石さんは国内外、さまざまな戯曲で「母」を演じる経験をお持ちですが、そこに何か共通するものはあるのでしょうか? 白石:そうですね……「母」というものは、所詮一つだなあという感じが少しするんです。母役を演じる機会は割合に多いけれど、根っこにある「ちょっと恐ろしいもの」が同じかなあ、と。そろそろ、そういうものから離れたいとも思うんですよ、単に「怖い女優」ってことになっちゃってるから(笑)。ただ初めて演じてから11年経って、もう一度作品と役に向き合えるわけだから、新しい扉を開けるのではと少しは自分に期待もしますね。ほら、今回は餌食が良いし、青山さんとの新たな出会いから「違う私を発見させて!」みたいな期待も募っているし。 青山:なんだかコワイなぁ(笑)。 中嶋:加代ちゃんは母性も豊かだけれど、実は少女性に満ちた方だから、その辺の感じがこのママ役にぴったりですよね。そもそも女は色んな面を持っているから、自分のことは分からなくても人を見ていると「女ってこういう生き物なんだ」と分かる瞬間がある。加代ちゃんを見ていると、能面みたいちょっとした角度で違う表情が見えてくる、「女って、こんな顔もこんな顔もするんだ!」と。隣りにいて、いつもそういうふうに拝見させて頂いていたので、そこに鏡のように自分の姿を映し、それに怯えたりしていればこの舞台は良いような気がします。 青山:中嶋さんが演じるジェシーも息子を持つ母親なんですよね。その点でも、母の役割や見え方が二重になる。 中嶋:そこがさらに面白いんです。 青山:同じ役割を持つ女性が、時に立場を逆転し、時には反転した姿を合わせ鏡のように映しあう。凄く良くできた戯曲ですね。 中嶋:互いに吐き気がするような瞬間もあるだろうし、堪らないですよ、こんな母と娘。 ――そんな母と娘、女性同士の間に青山さんは男性として立つわけですね。 青山:ええ、一種の神秘性を感じます。母子、女性同士の関係性も神秘だし、最初から最後まで物語を貫く「自殺」という主題も神秘でしょう、人間にとって。僕にとって生と死のふたつは同様の神秘で、そのふたつの謎を巡って演出家として何ができるか、何を見ることになるのか、それだけでも期待は膨らみます。
――映像と演劇、つくる過程に明確な違いはあるのでしょうか? 青山:映画はね、シナリオを書き、撮影・編集して公開するとゴール。演劇も本を読み、稽古をして幕が開ければゴールすることは同じなんですが、その後、僕の頭の中に残るものが違うんですよ。 白石:それは面白いですね。舞台の演出家は「ここに人がいるから、貴方はこっち」などというミザンセーヌ(動きの演出)を、言葉より優先して考える方が多いような気がするから。私なんかは言葉にものすごく興味があるほうだけれど、朋子ちゃんはどう? 中嶋:私は……全体の空気かな。 白石:(間髪入れず)そうじゃないかと思ってた。ピッタリよね。朋子ちゃんの身体の周りの空気は特別よ。 青山:僕は、全体の空気は稽古場で出来上がるに違いないと思っているところがあって。実際に稽古場で「よし、コレで行ける!」と、もちろん遠く、客席から見える距離感を考慮したうえで成立させるものなんですが、計算はある程度できるはずです。で、小屋入りしたあと「思ったとおり!」なんていう喜びがある。あとはそこに稽古場で幻視した「画」と、声や言葉が聞こえ続ける。もちろん両方でひとつなんですけど。 中嶋:多分言葉は「振動」だから、一番動いているもの・一番生きているものなんです。だから一番明確に覚えてらっしゃるんじゃないですか? 青山:そうかも知れませんね。あとね、右耳が聞いた台詞は右から、左耳のは左から聞こえるんです。 中嶋:面白い! でも「響き」ですから、当然かも。 白石:うーん、二人は似てるタイプね、この繊細さが。私なんか“ドバーッ”と行っちゃうタイプで激震ばかりだから。あー先が不安だ(笑)。 中嶋:嘘ですよ、加代ちゃん実はすごく繊細だもん。音で言うと“ゴーン!”と行ってから“シャラシャラシャラシャラ〜”って余韻が残る感じ(笑)。 白石:またまたぁ、私お二人に破壊されちゃうかも(笑)。 ――それにしても、次に青山さんの頭の中にこのお二人の声が住むというのは……贅沢ですね。 青山:本当に。またエラく長いこと住まわれてしまいそうです(笑)。
|
 |
 |
青山真治 白石加代子 中嶋朋子
|
| INFORMATION |
|---|