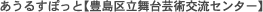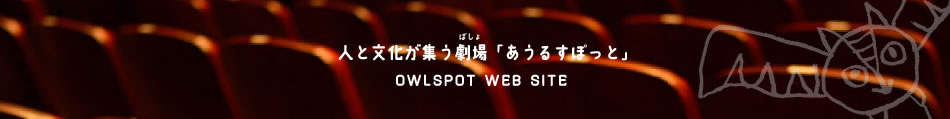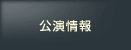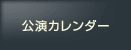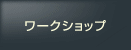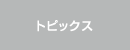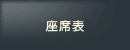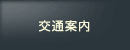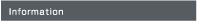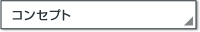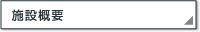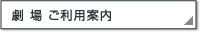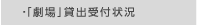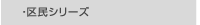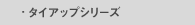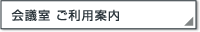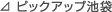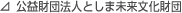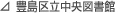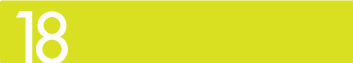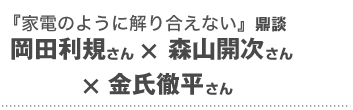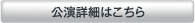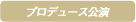トピックス・インタビュー18
|
現代日本の「リアル」を若者の生態を通して鋭く描き続けるチェルフィッチュの岡田利規さん。深く人間の内面を見つめ、その奥に潜むものを研ぎ澄まされた感性でダンスに昇華する森山開次さん。独創性の高いその創作が、海外でも高く評価されるアーティスト二人に、さらに新進気鋭の現代美術家・金氏徹平さんが加わった、「事件」と呼ぶべきユニットがあうるすぽっとで始動します。『家電のように解り合えない』。謎めいたタイトル同様に、予測不可能な創作の歩みを既にスタートさせているお三方に、それぞれの展望を伺いました。

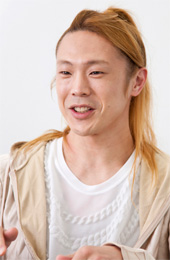

|
――非常に刺激的なコラボレーションが期待される方々がおそろいですが、企画の始まりはどのようなことだったのでしょうか。 岡田:あうるすぽっとから、森山開次さんと僕とで作品を作らないかという話を持ちかけられたのがきっかけです。で、美術をどんな人に頼もうかと考えてたら、舞台美術家じゃない人にしたいと思ったんですよ。演出家の意図をよく汲んでくれる人というより、その人のやりたいことを好きにやってくれる人がいいなと。もちろん、好きにやったその結果がすごくおもしろいことになりそうな人でね。それで金氏さんの名前が思い浮かんで、声をかけてみたら、乗ってくれたという、そういったわけでこのメンバーなんです。 ――それぞれどのようにな出会い、接点をお持ちだった他のでしょう。 岡田:2009年に僕が新国立劇場で演出した仕事(『タトゥー』)を作家の福永信さんと一緒に金氏さん一緒に金氏さんが観に来てくれたのが、最初ですね。 森山:僕との出会いは、岡田さんに2006年の僕のソロ公演『KATANA』をご覧いただいたのが最初だったと思います。自分で観に行ったのは2010年、横浜美術館で行われた『私たちは無傷な別人であるのか』ですね。「チェルフィッチュの舞台が面白い」という噂は周囲から随分聞いていて、僕は普段一人で創っているから、外の方の情報にはアンテナを広く張るようにしているんです。予備知識があまりないまま観に行ったんですが、とても面白かった。 金氏:それは僕も同じです。そもそも僕は、舞台などを観に行く機会があまりなかったんですが、岡田さんの作品には興味があったんです。実際、観た時も最初から楽しめて、無茶苦茶面白かった。なんというか「普通にわかる」感じがしたんですよね。そのあと急に、舞台を観る機会が増えました。 森山:僕は普段、色々と咀嚼しながら作品を創っているつもりですが、自分だけでやっていると、なかなか自分から脱却できない。「誰かにいじってもらいたい願望」がすごく強かったんです。演出されたいというか、自分ではないものを含めて創りたい。そう思いながら岡田さんの作品も観ていた。なんでしょう……僕がダンスで表現するということは、言い方に語弊があるかも知れないけれど、感情などを劇的に演出する、「芝居する」「創る」「ストーリーの何かを演じる」というような、創りながら要素を加え、幻想的な世界観を構築していくケースが多かった。 岡田:じゃあ、ぜひ喋ってもらいましょう! 今回は森山さんのダンスにしても、金氏さんの美術にしても、他のスタッフワークも、それぞれがやりたいようにやって、収拾が付いてないくらいのものになったらいいかなと思ってます。僕はそれらをちょっと整理するだけで仕事終わり、みたいな。 |
|
――既に岡田さん、森山さん、出演する俳優の方々でのワークショップが行われていますね。 岡田:ええ、少し作品のフォルムが見える瞬間もあって、良い時間を過ごしています。 森山:そこまでいくために、実はかなりの時間を積み重ねているんですけれど。どにかく動いてみる、題材のないところでも「何かやってみよう」ということの繰り返しですよね。 岡田:でもスルーしていても「良いな」と思っているものもあるんですよ。 森山:あ、あるんですか。でも、黙って引き下がるばかりじゃなく、僕の持ってる技や、一度はスルーされたものも違う形でリヴァイバルさせて、もう一回出そうみたいな、そういう事も考えてはいるんですけれど。同時に今まで自分がダンスをやってきた振付的なもの、ダンスのスタイルに行き過ぎてしまうのは嫌。それも出しつつ、違う観点からの動きをやりたいんです。そこは自分でも楽しみながらやってます。だから“いじられ願望”は今かなり満たされていて、自分のM気質を再認識しています(笑)。 金氏:今、森山さんが仰ったことが僕にもよくわかるんです。確かに岡田さんから出て来る言語は難しい。説明というか、説明でもないのかも知れないけれど、それをどう拾い上げるかが、僕にとって、まだ難しい段階にちょっといる感じで。
|
   |
|
――岡田さんの言語をどう捉えるかがお二人のスタートラインなんですね。岡田さんは、お二人に対する言葉を、演劇の現場で使っているものと変えていたりはされるのでしょうか。 岡田:そういう器用なことはできないです。僕、岡田語しか喋れないので、参加者にそれを勉強してくださいと。まあ「お前が普通語を勉強しろ」って話なんだけど(笑)。まあ、基本的には言葉で伝え合うべきなんですが、僕が一番望んでるのは、僕が「こうして欲しい」と望んだこととは違っててもいいから、面白いと思えることが、たくさん出て来ることですね。だからその意味では、僕の言葉を正確に理解することはさして重要ではないんですね。僕の方法論を理解したり体現したりするよりも、そこからはみ出した自由なものが欲しい。 森山:それは僕らにとっても有り難い方針ですね。僕自身今回、自分の動きの出し方の視点を広げたいし、なおかつ広い意味では「ダンスで勝負する」ことにもチャレンジしたい。それに対して岡田さんが日々どういうジャッジをするのか、どこが共有できてどこができないのか、そのせめぎ合いが一番大変で、面白いところでもありますよね。 金氏:ワークショップから本番の、一回ずつの公演まで、きっと作品は変わり続けるんでしょうね。でも、その「変わり続ける」という感覚は実は元々僕は意識していることなんです。使うのはコラージュのような方法ですが、そこにたとえば「石膏をかける」「珈琲のシミを使う」など、自分の思い通りにならないもの、「ひとつの現象を丸ごと切り取って持ってくるような感覚」を前から取り入れているんです。 ――創作の過程で変遷する動きや作品の構成に金氏さんが触発され、作品も進化・増殖していく。 初日と千穐楽では違うくらいに、と。 金氏:そうですね、できればそのくらいやりたいです(笑)。もしくは、そういう変化の可能性を受け入れられるような「場」をあらかじめ作っておく、ということも考えられます。 ――ちなみに今作のタイトルには、どのような意図が込められているのでしょう。 岡田:これはワークショップ・リハーサルを見てただの勢い的に、「理由は不明だけれど家電が壊れやすい部屋」という状況を思いついたんですね。家電って、テレビにしても冷蔵庫にしても洗濯機にしても、すごく自分の生活と密着してるのに、それが作動する仕組みとかよく分かってないじゃないですか。だから、ある意味で他者ですよね。なんとなく、そんな存在について考えてみようかな、と思って付けたんですね。まあ、ただのノリです。 ――今の岡田さんの思考の展開が、言葉になり、舞台上で用いるテキストになる、と。 岡田:はい、そうですね。ところで僕ね、自分が作るものがよく「美術的」「ダンス的」「音楽的」などと言われることがあるけど、でも正直な話、演劇を創っているというつもりしかないんですよね。なのにどうしてそういうことが起こるんだろうってことを、自分に都合よく解釈すると、たぶんそれは、僕の作品が演劇のポテンシャルをそれなりに顕在化させているからだと思うんです。でそうすると、美術的にとかダンス的にとか音楽的にとか見える。でも、それは単に、演劇という表現が高いポテンシャルを持っているからだけなんじゃないかと思うんです。 |
 |
 |
岡田利規 森山開次 金氏徹平
|
| INFORMATION |
|---|
|