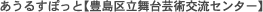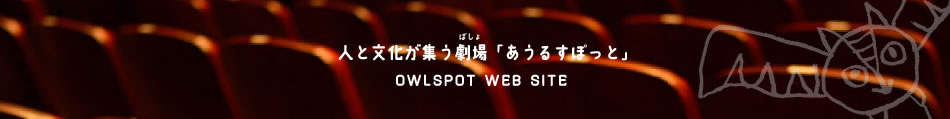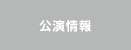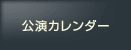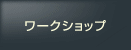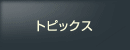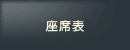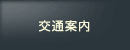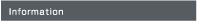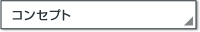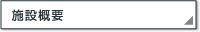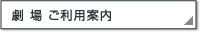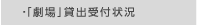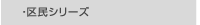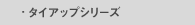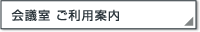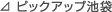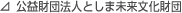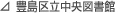- ホーム
- 公演情報一覧(2015年)
- SOMAプロジェクト
- 乗越たかおさんによる稽古場レポート(第3回)
公演情報
|
 200人以上の応募があったオーディション。 全てはここから始まった。 |
――いよいよ上演間際ですが、作品の仕上がりはいかがですか。 ファビアン(以下、「ファ」):「とてもいいですよ。1時間35分くらいになる予定ですが、じつに多彩な要素が作品の中で息づいています。日本とドイツの出演者たちもひとつのカンパニーとして強いつながりを持ち、誰もが舞台上で強い存在感を示してくれています。ホームステイも楽しみながら学びあうことができたようで、この企画自体の成功を確信しています」 |
――前回のインタビューで、パスカルは「ドイツ側のプロフェッショナルなダンサー達と日本側との身体のすりあわせ」について話していましたが。 ファ:「なんの問題もありませんでしたね。日本チームにいろいろな課題を与える中から、じつに魅力的な動きが次々と出てきましたから。そこからヒントを得て動きを作った部分も少なくありません。この作品はプロジェクト参加者全員で作ったもので、私は「共有する意識と身体によるコミュニケーション方法」を見つけられた気がします」 |
|
 二つの国のアーティストが、ホームステイを 経て舞台で交わる |
――日本チームについて伺わせてください。蘭妖子さんはアングラ演劇の大御所で、最年長・他ジャンルからの参加でしたが、いかがでしたか。 ファ:「彼女は特別な存在感を持っていますし、信じられないくらい魅力的な動きもできる人です。なにより70歳を超えて新しいことに挑戦する勇気は、深く尊敬します。私は彼女を特別扱いはしませんでしたし、作品に必要なことは遠慮なく要求してきました。出演者は皆対等なプロでなければならないからです。しかし彼女は喜んでそこに挑戦してくれていたと思います」 ――他のメンバーはいかがですか。 ファ:「俳優の大窪晶は身体的な強さがあり、他の人の何倍も課題を与えましたが、がんばってくれました。また谷川清美・中澤陽・あゆ子たちにも共通していますが、『日本人は自分の身体に対してとても賢い』という印象を受けました。自分の身体が持っている物を実にクレバーに、効果的に使っていくのです。前にも言いましたが、本作において、出演者は自分で自分の居場所を作らなければいけません。そして皆が作品に対して、積極的に自分の能力を提供してくれました。それがこのプロジェクトの目的のひとつでもあります」 |
 |
――音楽の二人(井ノ上孝浩、宇澤とも子)のことは、初めから高く評価していましたね。 ファ:「その通りです。とも子が複雑な音の構造を作り、そこに孝浩が楽器一つで人間性を持ち込むという、じつに素晴らしい関係です。ほとんどの人は『この二人は相当長いこと一緒にやっているのだろう』と思うでしょうね(笑)。初めは自由にやってもらいましたが、創作が佳境になってくると、私からの要求も色々加わってきます。でも「これでいこう」と決めた後も、とも子は少しずつ工夫を加えてくるんですよ(笑)。私もダンスで同じことをするので、その気持ちはよくわかる(笑)。形は決まっているけれども、作品が絶えず進化していく余地を残しておくのです。本作で音楽の果たす役割がいかに大きかったか、観客に伝わるようなシーンも作りました。」 |
|
――ドイツチームはこのプロジェクトを通してなにか変化はありましたか? ファ:「彼らとはピナ・バウシュのカンパニーで以前から一緒でしたが、クレモンティーヌ・デリュイとトゥスネルダ・メルシーはこういう形で私の作品のクリエイションに関わるのは初めてなので、変化はわかりません。しかし素晴らしいアーティストだとあらためて思いました。パスカル(メリーギ)とは何度も一緒にやっているので、よくわかっていますが、変わりませんね。パスカルは、何があってもパスカルです(笑)。 」 ――では作品についてもう少し伺わせてください。前回は「身体の中に分け入っていく」というイメージが語られましたが、それは古い映画『ミクロの決死圏』(1966年。原題「Fantastic Voyage」。超小型化した潜航艇で体内を巡っていくSFの傑作)を思い出す人もいるかもしれませんね。 |
 光と音と身体が、様々なレベルで交錯していく |
|
ファ:「面白いですね。実はこの企画の始めの段階では、ドラマトゥルグのマーク(ヴァーゲンバッハ)と、まさにその映画の話をしていたんですよ! 実際『身体の中に入り込んで、内部から身体を発見する』という意味では、非常に似ている部分があります。 ――ただ一般の人は、普段は身体のことを意識していないものですよね。二日酔いの痛みで初めて胃の存在に気づくとか。そうした観客に対して、この作品は何を訴えるのでしょう。 ファ:「難しい質問ですが、もしも身体を意識していない人に身体の存在をアピールでき、満足感を与えられたら、それこそがダンスの使命の一つではないでしょうか。私はスポーツを見るのが好きですが、それば極限の身体の使い方に触れられるからです。しかもダンスはストーリーを使えます。この場合のストーリーとは、『観客が自分の想像力を働かせることができる』ということ。スポーツにそれはありませんからね」 ――なるほど。楽しみです。最後に本番を前に、あらためてこのプロジェクト全体を振り返ってみるといかがですか? |
 サーモグラフィーが「見えない身体を視覚化」 |
|
ファ:「とても素敵なアドベンチャー(冒険)でした。これまでも日本とドイツのアーティスト、どちらか片方だけと仕事をしたことはありましたが、今回初めて一緒にできたのが良かった。両者の比較ができ、新しい発見が色々ありました。とても豊かで複雑に、そして複雑さがさらに豊かさを生むような毎日でした。 |
 プロジェクトを導いたファビアン・プリオヴィル |